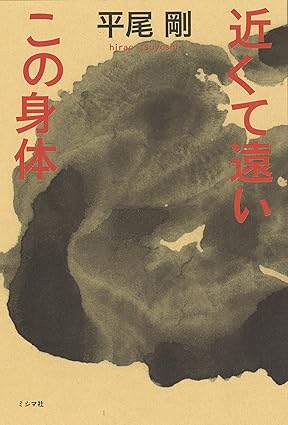『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
第6回 平尾剛さん(前編)『身体を問い直す――“近くて遠い”感覚とスポーツの未来を語る』

ラグビーでの経験から見えた身体の神秘、オリンピック開催への疑問、そしてスポーツの新たなかたち「スポーツ3.0」。アスリートとして、研究者として、スポーツをめぐる課題や可能性を深く見つめ続けてきた平尾剛さん(神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科教授)に、身体知について語っていただきました。
2025年3月30日開催のRES勉強会に平尾剛さんが登壇されます

身体に対する疑問を掘り下げた『近くて遠いこの身体』
RES ご著書『近くて遠いこの身体』(平尾 剛 著、ミシマ社)と『スポーツ3.0』(平尾 剛 著、ミシマ社)を書こうと決意された背景には、どのような問題意識や想いがあったのでしょうか?
平尾 自分の身体に起こったスポーツを始めとする経験って、実はわかっているようでわかっていない。身体って自分自身だからすごく近いというか、存在そのものなんだけども、わかってないことがいっぱいあるし、まるで人のものみたいに遠くに感じることもある。身体のことって、いざ説明しようと思っても言葉に詰まることがとても多い。という、身体にまつわる私自身の疑問を出発点にして書いたのが『近くて遠いこの身体』です。
ラグビー経験を言葉にしたいという強い思いもありました。なぜかというと、雑誌やテレビなどで他のアスリートが自らのパフォーマンスについて語る言葉が、自分の経験とフィットしなかったんです。例えばハイパフォーマンスの原因を「瞬発力がある」とか、「筋力がある」とか「判断力に優れている」みたいに、身体能力の高さで説明されたりしているんですけど、実際にはそんなに単純じゃないんですよね。ハイパフォーマンスって、偶発的な要素が絡んでくるんです、経験的には。ここぞという場面でふと数秒先の未来が見えたり、突然頭の中に声が聞こえたりして予測能力が働いたりする。自分ではない何か別のものに突き動かされてるようにプレーしているときにこそ、ハイパフォーマンスになる。いまだからこんなふうに言葉にできるけど、当時はほとんどできなかった。言葉にならない疑問をいっぱい抱えたまま引退してしまった。それならちょっと自分で書いてみよう。そう思いました。
スポーツ観の変遷を問い直す『スポーツ3.0』
平尾 『スポーツ3.0』に関しては、研究者になってしばらくしてから…たぶん2017年くらいですかね…、オリンピックのあり方について拭い難く大きな疑問を覚えて、それからずっとオリンピックの構造そのものを見直すべきだという主張をしてきました。その中で、東京オリンピックがコロナ禍で開催延期になり、翌年に強行開催されたことから、社会のスポーツを見る目がものすごくシビアになったなと感じました。私もスポーツ界の当事者として「こんな横暴なことしてたらダメだろ」って思ったし、社会情況を鑑みずに開催ありきで突き進むその様子を見て、スポーツを楽しめなくなりました。これは拙著の冒頭にもはっきりと書きました。
スポーツって、表向きは健やかで豊かなんですけど、その裏側では莫大な利権が絡み合っています。それを見直すためにも社会問題のひとつとしてきちんと書いておかなきゃなって思ったんですね。当事者であるスポーツ関係者が書くことでスポーツをバージョンアップさせたいという意図を込めて「スポーツ3.0」としました。
「スポーツ3.0」を説明する上でわかりやすい例えとしては、根性論です。根性論って、いまだに根強く信奉されていますよね。さすがに体罰は減りつつあるものの、暴言は増えています。その根性論を肯定していたのが「1.0」です。続く「2.0」は、根性論から脱却すべく科学的根拠にこだわった時代です。「水を飲むな」から「水を飲め」っていう指導に変わりました。ただ、やたらとその科学的な知見が入り込んできて、極から極に針が振れるように科学一辺倒になった。その最たるものが映像技術の発達と筋力トレーニングの導入です。
映像技術の発達にともない、どのチームも同じような戦い方を選択するようになりました。効率性を求めて勝利をするために最適な戦術や戦略が、ネットを通じて共有されるようになったんです。筋トレの導入は、筋力を高めるための効率的な体の鍛え方が、科学的根拠に基づいて確立され、それが広がっていった。つまり「根性論なんかいらない。科学的な根拠こそが絶対である」というのが「2.0」です。
でも人間って思考するものだし、、やっぱり心とか精神とかって大切ですよね。「根性」と言わずとも、「気持ち」とか「心構え」とかの心理的側面ってスポーツをするには欠かせない。気合いで乗り超えられることもままにある(笑)。もちろん、科学的な根拠に基づく考え方が大切なのは言わずもがなで、だからこそ、それらをきちんと融合していくような形で、これからのスポーツ像を描きたい。その新たなスポーツの姿を「スポーツ3.0」という言葉に託したのがこの本の要旨になります。

「科学的根性論」が示す新たなスポーツの姿
RES 「スポーツ3.0」の中にキーワードとして「科学的根性論」という言葉があります。これはやはり根性と科学サイエンスとの統合といいますか、どちらのいいところも取っていくという理解でいいのでしょうか? 根性と科学というある種二律背反なものを融合させて深めていくと捉えたのですがどうでしょうか?
平尾 そうです。例えば身体を鍛えるために、昔はうさぎ跳びや腕立て伏せなんかを強制的にやらされていました。つらさやしんどさを乗り越えてこそ身体は鍛えられる。いわゆる根性論ですよね。それがあるときから科学的な根拠のもとに、いわゆる運動生理学などの知見を用いて効率的に筋肉を鍛えるようになった。バーベルやダンベルなどの鉄の塊を持って、各部位を局所的に鍛え始めた。そして、筋肉を構成するタンパク質を摂取するためにプロテインサプリメントを飲み、筋肉の回復に必要な成長ホルモンの分泌を促すために良質な睡眠を取る。このサイクルを回して筋肉をつけるための方法が入ってきて、「科学に基づいて筋トレしたら、簡単に筋力がつく」となったんです。確かに、身体は大きくなり筋肉はついた。でもやはり筋トレには弊害があって、怪我しやすくなるんですね。
これはよくよく考えてみると当たり前の話で、部分部分で筋肉を大きくしたところで、すぐにパフォーマンスが上がるわけじゃない。肥大した筋肉同士を連携させてうまく使えないといけない。これを全身協調性と言いますけど、部分の集合が全体になるわけではないんです。
これは振付家の島﨑徹さんがおっしゃってたんですけど、「どれだけ鉄の塊を持ち上げても、舞踊の中で一緒に誰かと踊るときのリフトがうまくできるわけじゃない」と。「それだったら子供を持ち上げたらいい」と。「子供で軽く感じるようになってきたら、成人の人を持ち上げる」とか、いわゆる“生身の体に触れる”トレーニングを入れたほうがいいという話をされてたんです。まさにそういうことで、科学的根拠に頼るのではなくあくまでも「身体実感」を大切にする。ダンベルやバーベルを使わざるを得ないのであれば、持ち上げている時に身体の内側から発せられる声に耳を傾ける。旧来の根性ではなく精神や心、あるいは意識というものを軸に体を使う。それが “科学的な根性論”で、この構築は「スポーツ3.0」の柱になると考えています。
実際に今スポーツ界を見渡すと、例えばプロ野球選手でも筋トレをしない人も増えてきています。代表的な人で言えば、ドジャースの山本由伸投手ですね。山本選手は、ダンベル、バーベルを持たないんですよね。どういうトレーニングをしてるかというと、ブリッジの状態を保ちながら、右手を上げる、左手を上げる、右足を上げて筋力を鍛えるメソッドで、自分の体を鍛えている。おそらくバランス感覚を重視しているんでしょうけど、身体実感を手放さずにトレーニングを選んでいるところが、「スポーツ3.0」の実践者だと思っています。
数字やテクノロジーは決して否定されるものではなくて、一つの指標にはなると思うんですけど、日常的に感じている身体感覚こそに信を置くことが大切です。
「スポーツ2.0」と科学的アプローチの功罪
RES 根性論から効率的な世界に移る。これがスポーツ2.0だと思うのですが、これ自体にはやはり一定の根拠があって、人間の体のバイオメカニズムとかいろいろ理解が進むことによって、より運動能力を上げることができる側面もあると思います。そういう側面を追求する方々の中に、今の「身体実感」みたいなものが感じられないままやってるわけではないとも思います。その上で科学的方法論に行き過ぎていると感じられるのはどの辺りなのでしょうか?
平尾 身体運動がどんどん洗練されていく、どんどんうまくなっていく運動習得のプロセスは、個人差はあると思いますけど、基本的には一進一退ですよね。これまでできていたことができなくなるプラトーと呼ばれる停滞期は必ず訪れるし、プラトーが行き過ぎればスランプにもなる。リニアにではなく、ジグザグに進むんですね、運動習得のプロセスは。
これは赤ちゃんの成長過程の研究で明らかになっているのですが、生後3ヶ月の手足の動きと半年後を比較すると、半年後の方が手足が動く範囲が狭まるんです。だけれども、そのまた半年後にどうなってるかというと、右手と左手が連動して胸の前で握り合ったり、あるいは両足を一度に動かすような動作が、いわゆる高度な動きができるようになっている。つまり、停滞期のあとに動きの質が高まる。停滞もしくは後退するのは、動き方を整理し、より複雑な動きをするための準備期間であって、それは中高生になってからでも同じです。
でも、これと比べて筋トレは、ほとんど右肩上がりに筋肉がついていきます。体重も徐々に増えてゆくし、持ち上げられるダンベルの重さも重くなっていく。変化や上達が数字でわかるという点で、一目瞭然なんです。ここに一つ落とし穴があります。
RES どういった落とし穴なのでしょうか?
平尾 筋トレは、たとえばベンチプレスが先月と比べて20キロ上がったとします。その間の努力は数値の推移として可視化され、それは右肩上がりです。運動習得のプロセスがジグザグに進むのとは対照的で、そのわかりやすさにはまってしまうんです。この気持ちよさがエスカレートしていくと、いわゆる身体感覚とか心のありようみたいな、曖昧模糊とした感じに意識が向かなくなっていく。身体感覚を掘り下げるときの我慢というかタメがきかなくなり、つまりコツやカンを洗練させることが疎かになってパフォーマンスが落ちるわけです。数値化や定量化がもたらすわかりやすさに慣れてしまうことで、身体実感に意識が向きづらくなるんです。
平尾 剛(ひらお・つよし)
1975年大阪府出身。神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なる怪我がきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論。
【主な著書】
『スポーツ3.0』『近くて遠いこの身体』『脱・筋トレ思考』(以上、ミシマ社)
『合気道とラグビーを貫くもの――次世代の身体論』(共著 内田樹、朝日新書)
『ぼくらの身体修行論』(共著 内田樹、朝日文庫)など