『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
第5回 安田登さん(後編)『「孤」と「あわい」が拓く日本人の身体論――西洋的“Individual”との対比から空海のゲシュタルト的思考まで』
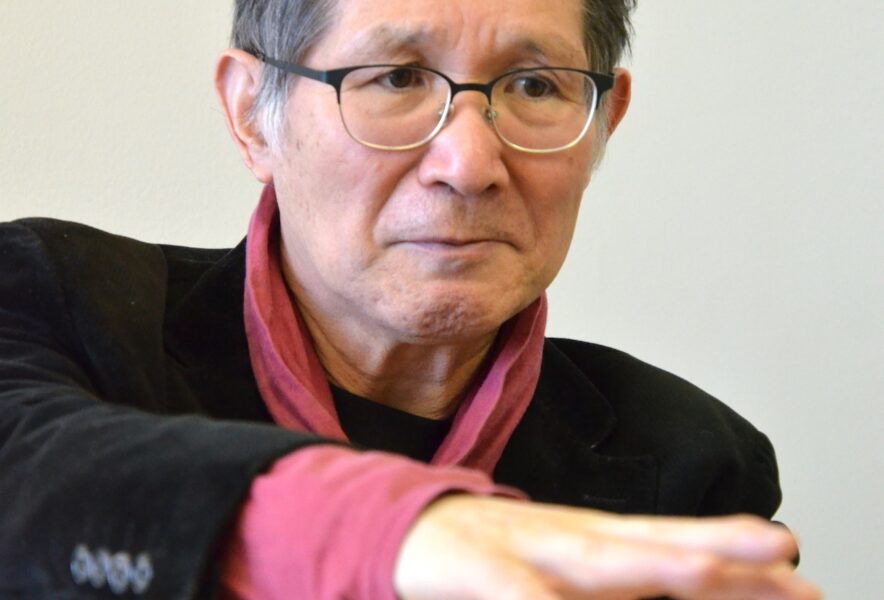
RES(教育サービス開発評価機構)の今年度のテーマは「身体知」。能舞台での調和や、不登校の子どもたちとの「おくのほそ道」の歩きなど、さまざまな実践を通じて見えてくる日本的な“孤”の価値。その背後には、西洋的な“Individual”とは異なる「あわい」の感覚があり、空海や最澄の思想とも深く結びついています。安田登さんが語る、日本人の身体性と学びのヒントとは――。(後編)
2025年3月30日開催のRES勉強会に安田登さんが登壇されます

SFが示す次世代の思考と身体性
RES 安田さんの方法論は非常に独自ですが、それを世の中に広げることについてはどのようにお考えですか?
安田 正直に言うと、広げたいとはまったく思っていません(笑)。ただ、今、高校生たちに甲骨文字を読む方法を伝えています。
RES どのような意図があるのでしょう?
安田 現代は、今までにない「新しい思考」が必要とされるときではないかと思っています。そのために「新しい文字」の発明が必要です。
新しい文字を考えるときには、一度、古代の文字、甲骨文字や楔形文字に戻ってみる必要があります。私の大学時代の専攻は甲骨文字だったのですが、甲骨文字はそれが出現したときには、すでに五千種類の文字がありました。常用漢字ですら約二千ですから、かなりの多さです。その中には動物や自然の形を象ったものが多くありますが、すでに抽象的な文字もできていて、当時の人々が世界をどのように見ていたのかを伝えています。
また、その筆写方法も特徴的です。甲骨文字と楔形文字に共通することは、それが立体的であるということです。「かく(書く)」という語も引っ掻くから来ていますし、ギリシャ語のグラフォー(書く:γράφω)もそうです。目で見なくても、指で触れることで読むことができる。
それが現代の文字は、平面的で、だからこそ視覚的なものになっています。これは甲骨文字や楔形文字ができたときから、こうなるべく作られていたのですが、その平面的な文字というものが私たちの思考方法までも決めてしまっているのではないかと思うのです。

たとえば甲骨文字の「馬」や「虎」、「象」などは、その動物を横から見た形で描かれています。「犭」も犬を横から見た形です。これは骨などの平面の上に写すために、その動物を2D化しました。
本当の動物は立体です。3Dです。それを2Dにするということは、比喩的にいえば微分することです。
しかも、その微分は恣意的です。同じ動物でも、「牛」や「羊」という文字は顔を正面から見た姿で描かれます。甲骨文字だけではありません。楔形文字の「牛」も顔を正面から見た形です。
これは「牛」や「羊」は角を数えるため、すなわち家畜として見ていたからことから作られた文字です。
微分を英語では「ディファレンシエーション」といいます。ディファレンシエーションというのは「分ける」こと。私たちが「分かった」というときがこれです。何か難しい話を聞いたときに、「もう少しわかるように説明してください」という。そうすると話す人は、複雑なことを単純化する、すなわち微分して話す。それを繰り返すと「わかった!」となるのですが、しかしそれは微分ですから、すればするほどいろいろなものが捨てられていくのです。
で、微分されたものを脳内で積分すればいいのですが、微分されたものを積分すると積分定数がついちゃうでしょ。同じにはならない。これも比喩的にいえば、みんな勝手なインテグレーションしちゃう。一度、「わかる=微分」されたものは、もとのものにはならない。だから必要なのは、ディファレンシエーションしない理解の仕方。ゲシュタルト(*2)的理解です。
複雑なものを、複雑なままに理解する。そのためには、文字自体を作り直さないといけない。2Dの文字ではない。じゃあ、3Dの文字かというとそんな簡単なものではない。それを考えるのは、その次の世代の子どもたちであって、そのためにまずはメディア自体が違っていた最初期の甲骨文字や楔形文字を高校生に読んでもらいたいと思っているんです。
RES すごい学びです! ここにはやっぱり身体性が孕んでいる。
安田 『あなたの人生の物語』(テッド・チャン、浅倉久志・他訳、早川書房)というテッド・チャンの短編集があるのですが、その中の「理解」という短編に出てくる主人公レオン・グレコは、氷水の中に1時間以上いたことによって脳に致命的な損傷を受けて植物状態になります。が、ホルモンK療法によって、その能力(脳力)はむしろ驚異的に進化し、なにを学習しても、瞬時にそのパターンを見てとる力をゲットします。彼は「数学でも科学でも、美術でも音楽でも、心理学でも社会学でも、あらゆるもののなかに、その統一的全体像(ゲシュタルト)が、音符の織りなすメロディが見えるのだ」と書かれています。
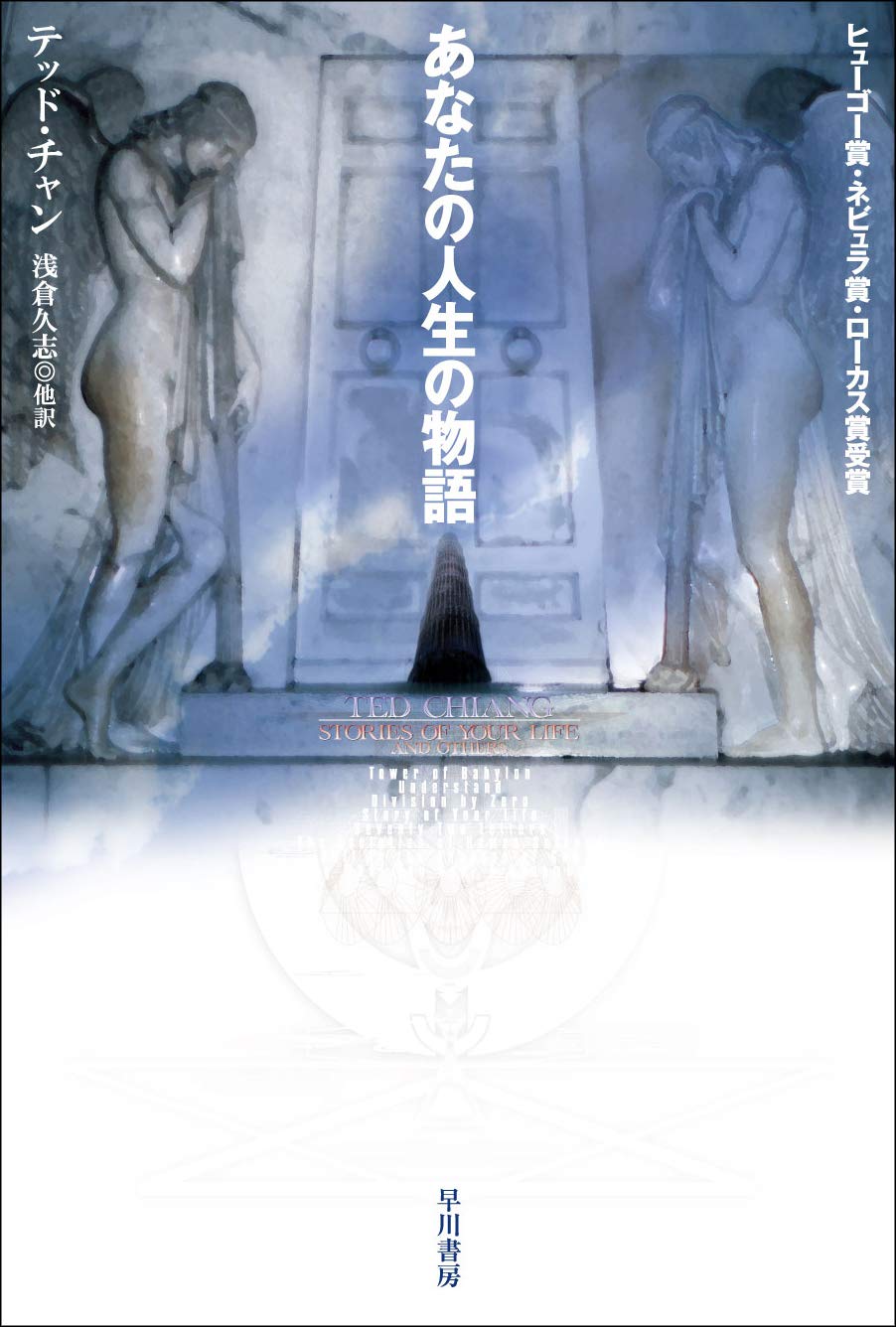
(テッド・チャン、浅倉久志・他訳、早川書房)
これがゲシュタルト的理解です。この能力があれば、あらゆることを瞬時に学ぶことが可能になるし、学んでないことですら学び得る。知的能力だけではありません。それは高い精神能力の発達を促し、それによって身体能力も発達し、どんなスポーツマンよりも高い能力を示すようになります。腎臓機能、栄養吸収、腺分泌といった身体の働きを感知できると書かれています。
これって今では、まだSF的な話ですが、次世代の理解の仕方はこうなると思うのです。そして、このゲシュタルト的理解に若き空海が学んだ「虚空蔵求聞持法」を思い出す人も多いのではないでしょうか。
RES なるほど! だから大日如来なんですね! それが「孤」の話に戻ってくると。
安田 しかも空海は、当時の人は自分が得たその力を理解できないと思って、それを冷凍保存させた。それが「即身成仏義」であり、「両界曼荼羅」なんです。私たちは、そろそろそれを解凍しなきゃいけないんじゃないかと思っています。
空海と最澄――ゲシュタルト的理解の継承問題
RES ちょっとまた話が飛んでもいいですか? 空海と最澄の死後、彼らがどのように受容されたかといったとき、残ったのは比叡山。やっぱり高野山はメジャーというよりはマイナーなわけですよね。何だかんだいっても、鎌倉仏教は全部比叡山。そういう意味では密教の表裏をどういうふうに今の文脈で理解されていますか?
安田 「源氏物語」の時代、当時の高野山はかなり疲弊していて、雷が落ちて焼け落ちても、修復するお金もない。藤原道長が夢に見て訪れるのですがびっくりした。ボロボロで。こうなった理由は、私は空海にあると思っています。彼は凄すぎた。空海は、全部理解していた。ゲシュタルト的に理解していたわけです。ゲシュタルト的に理解していたけれども、ゲシュタルト的に記述する言語はなかったし、今もない。
『理解』の主人公レオン・グレコも、自分の思考を記述する言語が「いま」はなく、「新たな言語の考案にとりかかっている」と言います。しかし、その能力をもってしても、その言語の発明はできなかった。こんなこと言うと真言宗の方たちに叱られると思うのですが、多分、誰も空海を誰も継げなかったのではないかと思うのです。
RES 継げなかった?
安田 あまりにもすごくて。
RES 覚鑁はどっちかっていうと俗化させた?
安田 おそらく。
RES やっぱり空海の後に空海はいなかった?
安田 そうです。最澄がすごいのは、途中で終わっちゃったことだと思うのです。これはひょっとしたらわざとかもしれない。完成して閉じるのではなく、開放で終わった。だから、みんなその遺産を継ぎながら、自由自在に動けたのではないかと思います。また、天台宗の教義って、とても複雑ではありますが、すごくディファレンシエーションされていますでしょ。理解は大変だけど、しかしわかる。難しいけど、わかりやすい。その難しいのも良くて、勉強する気になるんですよね(笑)。
空海は頭が良すぎて、説明の省略がかなりあります。『即身成仏義』などの著作では、解説が省略されている部分が多い。彼の思考を理解するには、サンスクリット語や仏教哲学を踏まえていることが必要になります。「この論を読む人はサンスクリット語ぐらい知ってるだろ」っていうのが前提になっている。今日は曼荼羅については詳しくお話している時間がありませんが、これも動きのある瞬間を冷凍保存させてたもの。私たちがそれを見るときには、動きも含めて見る必要がある。これもゲシュタルト的です。

RES 妙な質問になりますが、空海のゲシュタルト的な理解は、どのように現代に応用できると思われますか?
安田 空海のゲシュタルト的な理解に至るには、文字や言語も含めた理解の仕方がもう一次元上がる必要があり、それにはひょっとしたら脳そのものの変容も必要になると思っています。しかし、空海はそれを『即身成仏義』の中でもう少しわかりやすく説明してくれています。そのひとつが「三密」の考え方です。
それまでの仏教では成仏するには「三劫」という無限に長い時間が必要だと言われてきましたが、空海は「この身このまま」で成仏が可能だといいました。その方法が「三密」です。三密というのは、簡単にいえば仏の「身体」、「言語」、「思考」と一体化するということであり、その方法を詳述しています。これは、現在の教育や学習方法に多くのヒントを与えてくれると思います。彼の思想は単なる知識の習得ではなく、身体と環境、そして宇宙の全体性を捉えるものでしたから。
しかも、空海はサンスクリット語の「識(√jñā)」という概念を、「わかる」というディファレンシエーションの「知識(vi-jñāna)」がそのまま、全体を包括する「智慧(般若:pra-jñā)」に変容し得るとしています。どんな人でも悟った人になれる。いま「どんな人にも教育を受けられる機会を」といっても、ある大学に入るには、ある成績を取らなければならない。そこには当然のように知識の差別があり、それを差別とすら感じていないのが現代です。しかし、その差別すらもないという空海の考えは、現代の教育にこそ必要な視点だと思います。
熟達と“三流のススメ”――複数の専門性をもつ人材像
RES また、最近の人たちは「頭で考えるようになり、腹で考えることが減った」と『日本人の身体』で書かれていましたが、「腹で考える」とはどういう意味なのでしょうか?
安田 ひとつは「腑に落ちる」という理解の仕方です。「腹落ちする」、つまり「ああ、そうだ!」と深く納得する感覚を持てるまで考えることが大切です。Eテレの『100分de名著』で『平家物語』『太平記』『源氏物語』で講師をつとめましたが、私は専門家ではありません。だから、それに対してどんなに詳しい説明をしても、誰かの言ったこと、書いたことの焼き直しにしかなりません。まずは、「おお!そうなんだ」ということを探ることを意識しました。
RES その伝え方は再現性のある形に仕上げているのですか?
安田 そうですね。まずは、自分がその作品をとても好きになる。目についた本は、ほとんどすべて買います。そして、それを誰にでもわかるように書く。私の最初に売れた本は身体系の本なんですが、これはちょうど娘が中学2年生のときに書いた本で、原稿を書いているときには彼女に読ませて「わからな~い」といわれたところは全部書き直しました。中学2年生が理解できる、それが大切です。
RES ひたすら相手のフィードバックを踏まえて修正していくんですね。だから安田さんの著作は読みやすいわけですね。
あともう一つ。「体力という言葉についても違和感」をお持ちだとおっしゃってるんですけども、これは何でですか?
安田 「体力」については、文科省も厚労省も明確に定義ができていません。イヤなことをするとすぐ疲れちゃうし、楽しいことだと疲れも忘れる。体力は定義づけできないと思います。
能楽師は高齢のイメージがあると思いますが、早い人では3歳くらいから舞台に立って、そして93、4歳の方が普通に舞台をされています。だからといってスポーツクラブに通って体を鍛えたりはしていません。現代では筋肉をつけることが体力があると思われがちですが、筋肉は断裂して再生する過程で強くなるので、年齢によってはむしろ逆効果です。
RES なるほど。能楽師の身体性はどのように培われるのでしょう?
安田 これを説明するには、稽古とレッスンの違いを説明するのがいいかもしれません。一言で言うと、レッスンが「上達」を目指すのに対して、稽古は「熟達」を目指します。
上達というのは、どんどん上に行く。が、何かあったときに、例えば病気になったりすると、もう上に行けなくなる。年齢もそうですね。ある程度の年齢になると上には行けなくなる。そうすると、ポキッと折れてしまう。ところが、熟達は比喩的にいえばね、横に広がっていく。だからどこで終わっても大丈夫なんです。
能の舞というのは陰陽を繰り返している。前に行く陽の型をすると、次は後ろに行く陰の型をする。次に左に行くという陽の型をすると、次に右に行くという陰の型をする。
陰陽の型を繰り返すことによって、自分の中の陰陽を整えるんです。そして、自分の中の陰陽が整えば世界の陰陽も整う。それが能の舞です。
RES さっきのゲシュタルトみたいな世界観っていうのは、結局あらゆる環境に対して開いたり閉じたりできるということ。だとすると、上も下もないっていうことで、一体化していくかどうかっていうのが熟達。上達は、ある技能が深掘りというか、磨かれていくという世界になって、逆に言うと、それ以外できない世界になってくる。
安田 私は2年前に『三流のすすめ』という本を書いたんですが、これは魏の曹叡の時代に書かれた『人物志』という本を元にしています。この『人物志』は不思議な本で、中国ではすごく読まれているのに、日本では全く読まれていない。歴史でいうと、長岡京の時代には読まれていますが、それ以降の平安時代には読まれていない。で、これは何の本かと言うと宰相学の本です。天皇が学ぶのが帝王学だとすると、宰相(大臣)が学ぶのが宰相学。そう考えると、平安時代の藤原良房以降、実質的な宰相はずっと藤原北家なんで、たぶん彼らだけは読んでいた。他の人には読ませる必要がないし、読ませたくない。
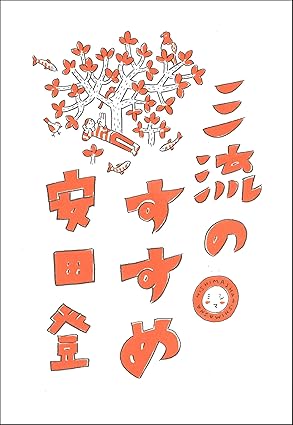
RES なるほど。
安田 今なら本当は、総理が読むべき本なんです。この本の中では「一流」というのは一つの専門家であると書かれています。そして、そういう人に国をまかせてはいけないと。例えば、法律の専門家に国を任せると、法に外れたものはすべて「悪」だと思う。でも、国家の経営ってそんなに簡単に割り切れるものではないでしょ。二流もまだダメ。で、諸流。つまり三流以上、3つ以上の複数の専門性を兼ね備えた人材こそが、社会を導ける存在だと『人物志』には書いてあります。
RES まさに上達というのは、一つの専門家になりがちだということですね。
*2 ゲシュタルト
構成主義・要素主義の立場では、人間の心理現象は要素の総和によるものであり、視覚・聴覚などの刺激には、個々にその感覚や認識などが対応していると考えられている。例えば既知のメロディを認識する過程では、一つ一つの音に対して記憶と対照した認知があり、その総和がメロディーの認識を構成すると考える。
これに対する反論としては、移調した既知の旋律であっても、同じ旋律であると認識出来る事の説明にならないというものがある。一つ一つの音は既知の旋律とは違っていても、移調しただけであれば、実際は同じものであると人は認識できる、というものである。
この事を説明するために提唱されたのが、ゲシュタルト性質という概念である。
ゲシュタルト心理学の最も基本的な考え方は、知覚は単に対象となる物事に由来する個別的な感覚刺激によって形成されるのではなく、それら個別的な刺激には還元出来ない全体的な枠組みによって大きく規定される、というものである。ここで、全体的な枠組みにあたるものはゲシュタルト(形態)と呼ばれる。
例えば果物が書かれた絵を見て、それが線や点の集合ではなく「りんご」であるように見える事や、映画を見て複数のコマが映写されているのではなく動いているように見える事は、ゲシュタルトの働きの重要性を考えさせられる例である。
安田登(やすだ・のぼる)
1956年千葉県銚子市生まれ。能楽師のワキ方として活躍するかたわら、甲骨文字、シュメール語、論語、聖書、短歌、俳句等々、古今東西の「身体知」を駆使し、さまざまな活動を行う。
【主な著書】
『あわいの力~「心の時代」の次を生きる』『すごい論語』(以上、ミシマ社)
『異界を旅する能~ワキという存在』(ちくま文庫)
『能~650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)など。
