『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
インタビュー
第7回 諏訪正樹さん(慶應義塾大学環境情報学部教授)(前編)『身体が知っている—AIを超えるクリエイティブの本質』【インタビュー】

「AIにはクリエイティブなことはできない」と語る諏訪正樹さん(慶應義塾大学環境情報学部教授)。なぜAIが「着眼」や「創発」を獲得できないのかを明確に指摘。前編では、デザインスケッチやスポーツの身体動作、さらには日常の些細な行動に至るまで、「身体を通じて生まれる新しい認知」を研究テーマとして掘り下げるようになった背景を語ってくださいました。
2025年3月30日開催のRES勉強会に諏訪正樹さんが登壇されます

【教育サービスR&D勉強会 #005】身体知の時代 ~身体知が学びの新たな地平をひらく vol. 3~
https://www.youtube.com/watch?v=3j... powered by Peatix : More than a ticket.
「身体知」とAI――クリエイティブの本質をめぐって
—— こちらの 『身体が生み出すクリエイティブ』 について、まずお伺いしたいと思います。冒頭で 「クリエイティブとは身体知である」 とおっしゃっていますが、これはつまり 「AIにはクリエイティブなことはできない」 という意味として解釈してよろしいでしょうか?
諏訪 はい、そう思っています。
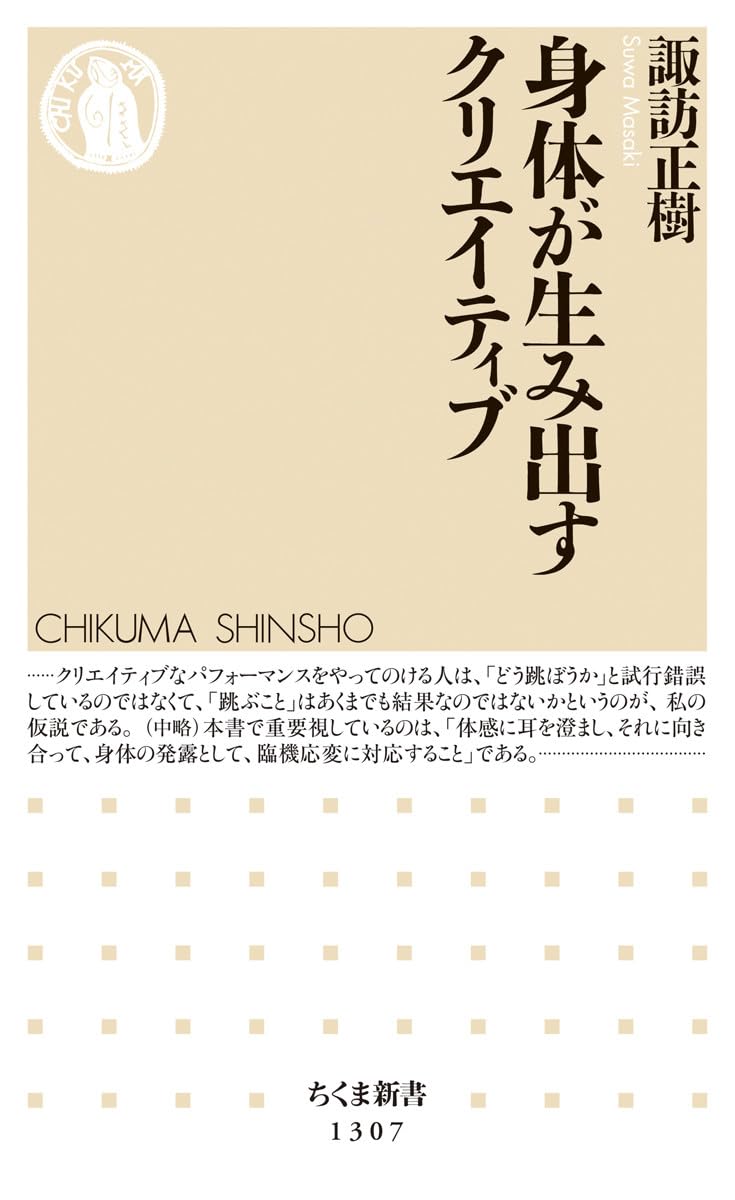
—— 「クリエイティブ」と「身体」というテーマを研究しようと思われたきっかけは何でしょうか?
諏訪 私はもともと AI の研究者としてスタートしました。かれこれ 30 年前です。当時は現在のような様相ではなく、「人間がどのような知能を持っているのか」あるいは「自分の知能を見つめる」という視点から、とにかく考察を重ねていました。自分が何かを行うときには、その知識はどのように身に付いたのかと考えたり、学んでいるときには、自分はどのように学んでいるのだろうと考えながら学んでいたりしていたのです。
私の場合、発想やひらめきのようなものに興味があって、発想する力とは何なのか、そして可能であればそれを AI にインストールしてみたいと考えていました。そうした経緯から最初に取り組んだのが初等幾何学の 「補助線を引く」 という問題です。補助線を引くのはある種の発想だと思いますし、私自身なぜか補助線を引くのが得意でパッと線が見えるひとだったので、どういうメカニズムなのかを知りたかったのです。
そこで、まず補助線の引きかたについての仮説を立て、それを知識の形に表現し、コンピュータにインストールしてみたら、ちゃんと補助線を引けるプログラムができたのです。人工知能学会の論文賞をいただいたのですが、1990 年です。
初めて書いた論文で、多くの方に「補助線を引けるプログラムがあるなんてすごいね」と言われました。しかし私にとってみれば、自分がどんな知識をコンピュータにインストールしたかを知っているので、「この知識があればそりゃ補助線も引けるよな」という感じで、まったくクリエイティブだとは思わなかったのです。
—— なるほど。
諏訪 そうして AI の研究を始めることになったのですが、同時に人工知能の限界にも気づきはじめました。そして「発想」にまつわるさまざまなテーマを探しているうちに、途中からデザインの例題に取り組みはじめたんです。建築家はデザインスケッチを必ず手で描きますが、スケッチはアイデアを生むうえで大きな役割を果たしていると。デザイナー・建築家・アーティストたちはクリエイティブそのものなので、彼らがどのようにスケッチを活用しているかを研究したのです。
実際に建築家がスケッチを描く様子をつぶさに観察し、どのような意図で描いているのかをすべて言葉で記録していくと、彼らがスケッチをどう使っているかがわかってきました。単に鉛筆を走らせて頭の中のアイデアを写し取っているだけではないと。
これから建てようとする建物の概略をスケッチでざっくり描いては、何度もなぞるという行為をしていると、描いたときには気づかなかった周りとの関係性にパッと気づくのです。興味深かったのは「なぞる」という身体的な行為そのものです。なぞるという行為については論文では詳しくは書かなかったのですが、なぞりながら自身のスケッチを見ていると思考がパッと広がるのは、明らかに身体が何らかの形で寄与しているのではないかという仮説に行き着いたのです。
そのあたりからもう、デザインとか人工知能が扱える論理的な問題などだけではなく、スポーツも例題にするようになりました。自分で言うのもなんですけど、私はある程度身体能力があるほうで野球を長くやってきました。投げる・走る・守るは得意なのに、打撃はあまり得意ではなかった。「なぜ打てないのか」という疑問を礎にして、自分が打つことを学ぶプロセスを研究課題に据え、そこから身体知の学びという領域を研究することになりました。
身体知研究の広がり――スポーツ科学を超えて日常へ
諏訪 一般的なスポーツ科学では身体がどう動いているかを研究する一方、ことばは一切扱いません。でもそれでは学習の研究にはならないわけです。「身体を使いつつ、ことばも使い、そして身体とことばの関係を自身で模索する」という私の身体知理論の根幹も、野球の打撃の学習プロセスの研究から形成されました。
さらに、スポーツのように身体をダイレクトに使う行為だけではなく、散歩とか、居心地を感じる身体感覚のような日常の行為も身体知のかたまりだということで、身体知研究として生活場面を取り上げるようになりました。
全ての研究例題において特徴的なのは、現在の思考・認識のフレーム——それは辞書といってもいいですが——をある瞬間にパッと飛び越える局面が必ず存在するということです。デザインスケッチの例でも、それまで紙面上のある要素のことを考えていたのに、それが別の場所に描いた要素とパッと繋がる瞬間がある。打撃のスキルの学びでいえば、バッターボックスで落ち着いて脱力することを考えていると、それはむしろ呼吸とか姿勢の問題かもしれないということになってくる。それはもう生活の話であって、単なる野球の打撃スキルの学習の域を飛び越えて、生活全般に亘る「生きるってどういうこと?」みたいなこと、哲学的なこともいろんな関係してくる。身体知とはそういうことだなとわかってきたわけです。
いまホットになっている概念の束(思考・認識のフレーム)の中だけにいるんじゃなくてフレーム外のこととつなげて考え・認識するというのが「着眼」という行為で、それがクリエイティブなことが起こり始めるきっかけではないかというのが、30年ぐらい前に私が得た思いの原型です。
一方で AI はどうかというと、プログラミングされた段階ですでに言葉・概念のセットが決まっているので、囲碁AI が将棋をできるわけではないし、野球もできないし、「カフェの居心地の良さ」を感じるわけでもありません。プログラムされた瞬間に認識フレームが固定なので、それを柔軟に広げたり狭めたりするのは原理的に不可能です。だからこそ、AI がクリエイティブなことをするわけがないというのが私の考えです。

AIには不可能な「着眼点」――データ化を超える人間の力
—— 一般的にAIにデータを読ませて、ラーニングさせるのが最近の主流だと思うのですが、そういうことも含めて、言葉の知識セットが決まってると言って良いですか?
諏訪 「データ」というのは人間が世の中から切り出したものですよね。AI はネットに転がっているデータをただ集めているだけで、データは世の中の現状そのものとは違う。世の中からデータを切り出しているのは人間。AIは既にデータ化されていることからは学べますが、世の中から自力で学ぶのは不可能であるというのが、まずひとつあります。
AI単独でクリエイティブである必要はないという意見は昔から言われていました。要は「人とAI との合わせ技でクリエイティブになれる」という考え方ですね。私もそれに反対というわけではありません。ただ、AI にデータを食わせるのは人間です。その人が「これをデータとして与えよう」と判断したものしかAI は扱えないわけです。人の頭の中にあるデータであれ、ネット上に転がっているデータであれ、すでに概念や言葉になっているものしか AI は利用できない。
—— そこを飛び出すことはできない。
諏訪 ひとの場合はクリエイティブなことが起こる瞬間は、ひょんなことで今まで自分の中でデータになってなかったことが急にデータになるんです。
—— それが「着眼点」ってことですか?
諏訪 そう、それが着眼点です。多分、物理的な身体や現場の状況、それまでずっと考えてきた思考の履歴や人生背景といったものが組み合わさって、パッと何かに着眼してしまう。すると、本人にとって人生で一度も目を向けたことがなかったようなものごとが急に「データ」として立ち現れる瞬間が訪れる。それがクリエイティブなものごとの始まりです。
人はそうやって新しいデータを生成し、その後 AI に与えることで、ある程度両者にとってクリエイティブなものごとが生まれていくけど、新鮮じゃないですよね。生まれた瞬間じゃないからね。
—— 作った人にとってはですね。
諏訪 しかも、AI に読ませる段階には、これは重要概念だと意識しているものごとを読ませるわけでしょ? 逆に言うと無駄だと思って捨てているものがいっぱいある。でも本人が無駄だと思ったのだけれど実は無駄じゃないってことはいっぱいあるわけです。
人の場合は、いったん意識上では捨てたはずのものをまた思い出して「もしかして……」と考え直すこともできます。だけどAIはできない。人は現在の状況、身体の状態、さらに、もしかして昨日食べたものにすら影響を受けながら、臨機応変に着眼を変容させられるけれど、AI にはそれが不可能です。
そういうのを認知科学の用語で「situated cognition(状況に埋め込まれた認知)」と言います。要するに、現場に立ってみないと何が着眼や思考・認識に寄与するかわからない。でも、現場に立ってみないと何が寄与するかわからないというのは、「認知のモデル化」ができないということでもある。situated cognitionの思想が出てきてもう30年以上になりますけど、モデル化してなんぼと思っている研究者はこの研究思想を敬遠してきました。
—— 科研費が取りにくい?
諏訪 科研費もそうだろうけど——しかし、ちゃんと書けば通るんですけどね——、とにかく「すぐ成果が見える」研究を求める風潮が強まると、situated cognition的な思想や研究アプローチは敬遠されがちですよね。
でも、それをちゃんと研究しないと人の知能の本質はわからないと私は思っています。クリエイティブといっても、デザイナーやアーティストだけの話じゃなくて、日々の散歩で思いつくアイデアとか、老後に新しい生きがいを見出すとか、そういう生活全般の気づきも十分クリエイティブなんです。そこには大いにsituatedな要素が含まれています。
—— ちょっと言葉の問題かもしれませんが、クリエイティブをその広い意味で捉えたとき、「創発」「気づき」「ひらめき」など、いろんな言い方がありますよね。最近は「アブダクション」という言葉もよく聞きますが、これと似ている点や違う点については、どう考えればいいでしょうか?
諏訪 アブダクションという言葉自体は、私が学生の頃からありました。例えば「AならばB」というルールを知っているとしましょう。B という現象が起きたら「あれ、じゃあAがあるんじゃないか」と逆を推測する。これがアブダクションですが、それには「AならばB」というルールが言葉として記述されていなきゃならないんですよ。つまり、いわゆる「アブダクション」と言われてきたものは、常に言葉で整理された世界の中で成り立っていて、そこから一歩も出ていない。
でも私が言う「身体知」とは、身体が状況に深く入り込んではじめて何らかの着眼が生まれる、そういった、既存のルールに基づく推測ではないものかもしれません。だから、一般的に言われるアブダクションと私の考えていることは違う気がしています。
何をもってアブダクションって言ってるか、アブダクションを言うときにどんな例題で語るかによって、私の説に近いか、30年前から言われてるアブダクションそのままかがわかるんじゃないですかね。
—— いわゆる「ルールをいくつも知っているから、それを遡ってみて推測する」というレベルのアブダクションと、何かルールの存在すら知らない状況で、新しいつながりがふっと生まれるような事態とは、性質が違うということですね。
諏訪 そうですね。私のいう身体知的な発想は、もしかするとインダクションとアブダクションを同時にやってるようなものかもしれません。
諏訪 正樹(すわ・まさき)
慶應義塾大学環境情報学部教授
1962年大阪生まれ。工学博士。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。(株)日立製作所基礎研究所、シドニー大学建築デザイン学科主任研究員、中京大学情報理工学部教授等を経て現職。身体知の学び、コミュニケーションのデザインを専門とする。
【主な著書】
『「こつ」と「スランプ」の研究』(講談社メチエ)
『身体が生み出すクリエイティブ』(ちくま新書)
『一人称研究の実践と理論 —「ひとが生きるリアリティ」に迫るために』(近代科学社)など。
