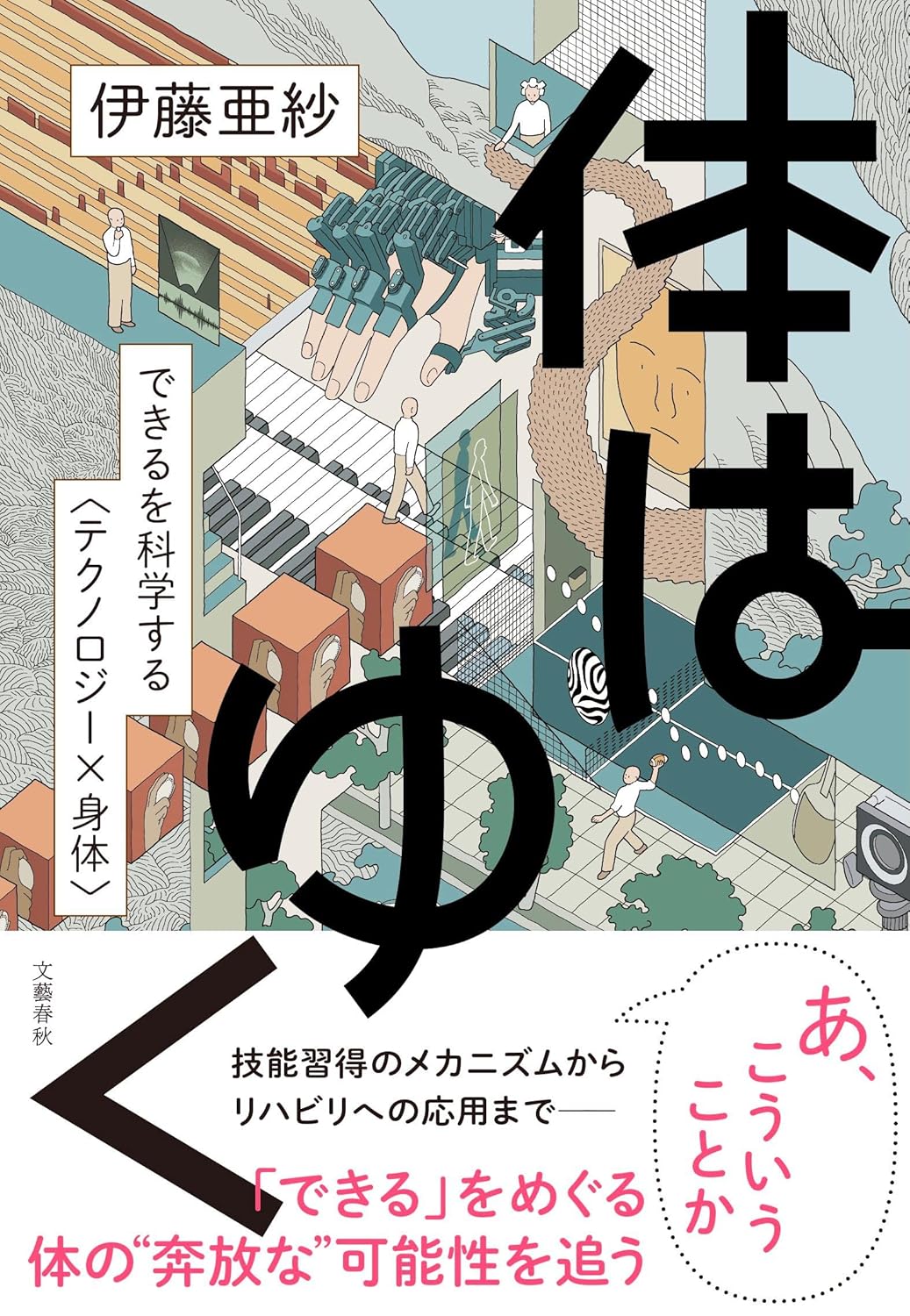『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
第6回 平尾剛さん(後編)『身体を問い直す――“近くて遠い”感覚とスポーツの未来を語る』

身体の育ち方も鍛え方も、人それぞれまったく違うからこそ「自分ごと」として捉えることが大切だ――。最新テクノロジーが進化を後押しする一方、個人の資質や痛み、感覚への向き合い方はあくまでも主体的であるべきだと語る平尾剛さん(神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科教授)。科学データでは捉えきれない「身体実感」をどのように言葉にし、競技力やスポーツ文化を深めていくのか。平尾さんはその問いに真正面から向き合ってくれました。
2025年3月30日開催のRES勉強会に平尾剛さんが登壇されます

「科学に丸投げしない」――自分の身体を主体的に捉える視点
RES 個人の資質によって必要なトレーニングは全然変わってくると思います。ご著書の中で「自分ごと化」というキーワードを挙げられていて、『テクノロジーに丸乗りするのではなく、あくまでも「このからだ」がどう反応するのかに重きを置く。科学的あるいは文学的な思考をくりかえしながら、「自分ごと」としてテクノロジーと向き合う。つまり、「このからだ」との対話をつづけながら、どのようにテクノロジーとつき合うのかが試行錯誤だ」という伊藤亜紗さん(東京科学大学教育研究組織 未来社会創成研究院・リベラルアーツ研究教育院教授)の言葉(*1)を引用されていました(『スポーツ3.0』P.210)。これに対して平尾さんは「大いに同意する」と書かれてたんですね。この真意、あるいはなぜ同意されたのかをお伺いできますか?
平尾 科学的な知見に丸投げすんなよっていうことですよね。身体って、当たり前だけど一人一人違います。頭と胴体があって腕も脚も二つという構造は同じなんだけど、内実はこれまでの成育歴やスポーツ経験があり、人それぞれ全然違うわけです。
例えば私は、度重なる捻挫で両足首ともに靱帯が伸びてしまっています。科学的に効果があってどれだけ効率的なトレーニングであっても違和感が拭えないし、違和感どころか痛みが出ることさえある。その痛みと向き合いつつ、自分に合ったトレーニングやそのやり方を工夫しないといけないんですね。それが“自分ごと化”だと思うんですよ。自分の「この身体」がどう感じているのか、どの角度なら痛みが出ないのかなどの観察から出発する。科学的に新しいトレーニング方法が開発されたとしても、それになじませていく主体性みたいなものがキーになる。それを伊藤亜紗さんはきちんと書かれていました。
この先どれだけテクノロジーが進化しても、あくまでもそれを主体的に使うという意識がないと、身体そのもののリテラシーは底上げされないというのが私の考えです。基本的に自分のものにしていくときには、やっぱり自分ごととして自分の身体を捉えなければなりません。自分の感覚でつかんで、反復して、無意識化する、身体化するという作業を端折ってはいけないし、そもそも端折れません。
言葉にしてこそ深まる「身体実感」
RES 「身体実感」の捉え方についてもお伺いしたいのですが、科学的なデータとして一つの指標が出てくることでわかることはあると思います。一方で、データにはでないアスリートや運動をしている人が感じる感覚もあると思うのですが、これを言葉にするのは難しい。その上で、これをどう扱えばいいと思われますか?
平尾 これは「鶏が先か卵が先か」という問題だと思っています。たとえばボールを投げるときに、「うまく投げられない」となると、うまく投げるためのコツを探りつつ意識は身体の内に向きますよね? 握り方がどうか、肘をどこまで上げ、肩をどのように回すか、あるいは体幹をどこまでひねればよいかとかを探ります。体の内側に意識を向けて感じを探りつつコツやカンをつかもうと試行錯誤するときには、ほとんど言葉は介在しません。この局面で頼るとすればおもにオノマトペになります。「グッと」握らず、「フワッ」と握ったほうがいい、みたいに。
その一方で、言葉が先にあって、それが身体実感を創発するケースもある。「卵をつぶさない程度に握るように」という指示から、ボールを握るときの適切な感覚を探ることができるわけです。こういう例え話、つまり言葉がきっかけとなって、目指す動き方を具現化するための「身体実感」がつかみやすくなるということがある。
とてつもない怒りを意味する言葉に「怒髪天を衝く」がありますよね。でもこの言葉を初めて知ったときには誰しもあまりピンとこないと思うんです。大きな大きな怒りを表す言葉なのはわかるけれども、身体実感としてはよくわからない。でも、実際に髪の毛が逆立つような激しい怒りを感じる経験をしたときに、ストンと腑に落ちる。カチンとくるのでもなく、胸のあたりがキュッとするのでもない、まさに髪の毛というか頭全体がカーっとなるような身体実感がともなう怒りのことなんだなって。
だから、こうした言葉をたくさん知っている、あるいは例え話をたくさん知っていることで、自分の身体の内側から感じられる感覚、心・身体実感がより豊かになると思います。つまり、実際にこの身体を使って動くなかで言葉を介さずともわかってくるルートと、言葉の意味を自分の体でつかむというルートがあって、この2つをぐるぐる回していくのが一番豊かな方法です。そういうふうにして、身体実感・身体感覚は研ぎ澄まされていくのではないでしょうか。
テクノロジーと伝統の融合が拓くスポーツの未来
RES 伝統武術、能などの伝統芸術の身体の動き、現代スポーツ、そこにAIやVR、ARなどのテクノロジーが融合することによって、今後の競技スポーツ、身体観はどう変わってくると思いますか? あるいは一般のスポーツ愛好家の楽しみ方とかも変わるのでしょうか?
平尾 たとえばVRでは野球のバッティングフォームを体感するみたいな技術がありますよね。あるピッチャーの球速やコースをVRで体験するとか。それ自体はすごくいいと思うんです。だけど、それを使ったら実際に打てるようになるのかというと、そこは微妙で、あくまで上達へのきっかけにしかならないのではないでしょうか。
とはいえ、きっかけは大事で、たとえ仮想体験であっても「今まで一度も感じたことのない感覚」だと気づくことができれば、その目新しい身体感覚を自分のなかに取り込もうと意欲的になります。先ほどの“自分ごと化”とか“主体性”とか“対話”にもつながるところです。どれだけ機械化したところで、野球だったらボールがバットの芯に当たった瞬間の、手の平から伝わってくる心地よい衝撃とかその音とかの「リアル」は、直に体感しないとわかりません。最後にその「リアル」を現実の身体のレベルに落とし込むという作業を経ないと習得できないんですけど、そこに至るまでにうまくテクノロジーを活用できれば面白くなると思います。
AIだって、例えばあなたのスイングは角度が何度足らないとか、骨盤が何度回転してないとか数値として教えてくれるかもしれない。それを参考にして、「じゃあもうちょっと骨盤を回してみよう」としてみると、実際に回してみたら痛みが生じたとか、かえってスイングが遅くなったとか、身体からはなんらかのフィードバックがある。それらを微調整していくなかで「いい感じでラクな動かし方」がみつかるんですよね。ああでもない、こうでもないと試行錯誤するのが“身体の学び”であり、身体リテラシーが高まるプロセスです。だからテクノロジーは否定しないですが、同時にそこに振り回されずに自分で最終的に落とし込もうとする意図がすごく大事かなって思います。むしろテクノロジーと融合することで身体の「リアル」が浮き彫りになる。そんな気がします。
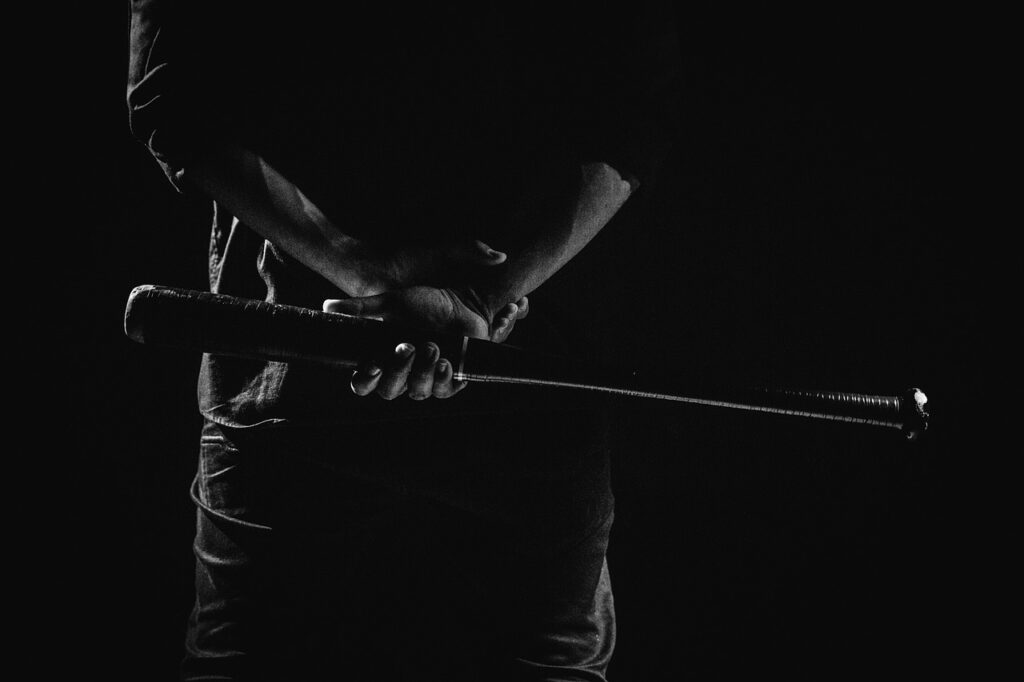
スポーツって、できないことができるようになったり、できていることをもっとできるようにしたりと、ちょっとずつ身体感覚を掘り下げていくプロセスが楽しい。ここにスポーツの本質があると私は思っていて、ゴルフやマラソンに興じるスポーツ愛好家たちは、すでにそれに気づいている。だから、あれだけ楽しそうに打ったり走ったりしているんですよね。
RES なるほど。バランス感覚が求められるように感じました。最後の質問になるのですが、今後研究したいテーマは分野を教えていただけますか? また、スポーツ4.0というビジョンはお持ちでしょうか?
平尾 まだ4.0は見えてないですね(笑)。3.0もまだまだ研究しなければいけないと思っているので。今はスポーツ3.0を下敷きとしてもっと具体的な中身を広げていきたいと考えています。その中でおぼろげながら4.0が見えてくるかもしれません。
研究したいテーマは、やっぱり運動そのもの、身体そのものの話ですね。ここ数年は、オリンピックの意義などスポーツを社会学的な視点から考えて、発信を続けてきたので…。もともとは身体論が専門で、「筋力に頼らないからだの使い方」を研究していました。なので、初心に立ち返りたいと思っています。あとは感覚と言葉の関係性についてですね。これを現象学的に掘り下げていこうと考えています。
研究するにあたって、昨今とりわけ念頭においているのが「言語化」で、当たり前なんですけどやはり大事だなと改めて感じています。言語化の重要性に初めて気がついたのは、ラグビー選手を引退するかしないかの時期でした。ブログを作ってそこで書き始めたら身体への理解がどんどん深まっていったんです。現役真っ只中は言語化してる余裕がありませんでした。たぶん多くのアスリートは、引退してしばらく経ってから自らの経験を語りたくなるんじゃないかなあって想像してます。
どこまでを言葉にし、どこまでを言葉にしないでおくかに慎重でありたい。また、わかりやすく伝わる言葉と、謎を蔵したままに緩やかに伝わっていく言葉を、効果的に使い分けたい。そんなふうに考えています。
*1:伊藤亜紗『体はゆく――できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』文藝春秋、2022年、P.205
平尾 剛(ひらお・つよし)
1975年大阪府出身。神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なる怪我がきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論。
【主な著書】
『スポーツ3.0』『近くて遠いこの身体』『脱・筋トレ思考』(以上、ミシマ社)
『合気道とラグビーを貫くもの――次世代の身体論』(共著 内田樹、朝日新書)
『ぼくらの身体修行論』(共著 内田樹、朝日文庫)など