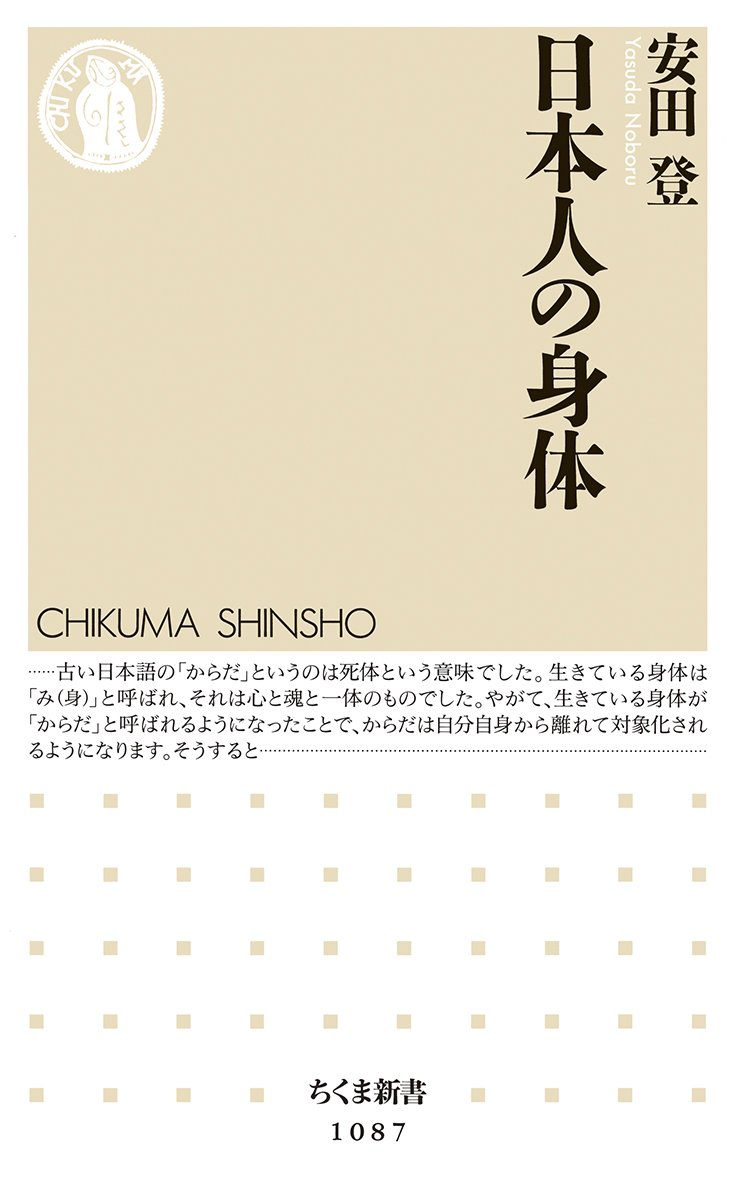『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
第5回 安田登さん(前編)『「孤」と「あわい」が拓く日本人の身体論――西洋的“Individual”との対比から空海のゲシュタルト的思考まで』

RES(教育サービス開発評価機構)の今年度のテーマは「身体知」。能舞台での調和や、不登校の子どもたちとの「おくのほそ道」の歩きなど、さまざまな実践を通じて見えてくる日本的な“孤”の価値。その背後には、西洋的な“Individual”とは異なる「あわい」の感覚があり、空海や最澄の思想とも深く結びついています。安田登さんが語る、日本人の身体性と学びのヒントとは――。(前編)
2025年3月30日開催のRES勉強会に安田登さんが登壇されます

「孤」と「和」の本質
RES 『日本人の身体』(安田登、ちくま新書)の中で、安田さんは「現代は、『孤』の道を歩んでいる」と書かれていますが、なぜそのように思われたのでしょうか?
安田 この本の中では、周囲との関係を拒絶するという意味での「孤」を使っていますが、しかし私はこの“孤”という言葉はとても重要な語ではないかと思っています。漢字の意味としてはみなしごの “孤”でもあり、そして独立した自己としての“孤”でもある。貴人は自分のことを「孤」と称していました。他者に責任を転嫁せず、自分がすべてを引き受ける「孤」です。そして、孤独を通して見えてくる強さや価値もあると思います。
RES 特に、安田さんが言及される「孤」は、単なる孤立ではなく、何か別のニュアンスを含んでいるようですね。
安田 そうですね。引きこもりの人たちと『おくのほそ道』を歩く活動をしています。その人たちの中には不登校の子もいますが、四十歳以上の大人の引きこもりの人もいます。社会からすると問題だと思われがちですが、しかし人と繋がらない強さみたいなものがある。「孤独」といいますが、「独(獨)」というのは、元々雄の動物を指す漢字です。雌は群れの中にいますけど、雄は独立している。群れが好きな人たちと、独りが好きな人たちがいるでしょう。学校などでも、みんなで一緒にすること、すなわち群れの重要性がいわれますが、しかし独りでいることもすごく大事です。彼らにはその力があります。
「孤」は歴史からみても非常に奥深いものがあります。聖徳太子は「和を以て貴しと為す」と言いました。この「和」はもとは「龢」という文字で書かれていました。この字は、違う楽器の音を同時に鳴らして、そこである調和をつくるという文字です。
RES 同じ音を出すんじゃなくて、違う音を出すことで作っていくのが「和」というわけですね。
安田 そうです。逆が「同」。同じ音を鳴らす。孔子は「君子は和して同ぜず」と言いましたが、聖徳太子も「和(龢)」の重要性を言いました。いまは「和」を「同」の意味で使っている人が多いですね。「和を大事にしろ!」なんていうときは。
でも、日本人も本当は「同」は嫌いで、「和」が好きだったのではないかと思っています。そして、それが「孤」なのです。
能の舞台に立つ人々は、それぞれ異なる流派に属しています。そして全員が異なる台本を持って各自で稽古をして本番を迎えます。解釈のための話し合いなんてしません。孤と孤がぶつかり合うことで新しい何かが生まれる。それが「和(調和)」であり、このプロセス自体が能の本質だとも言えます。
去年も海外公演があったのですが、空港まで一緒に行ったりしませんし、トランジットでも降りるとみんなバラバラになる。でも、むろん同じ飛行機には乗る。舞台はみんなでやりますけど、それ以外の時間はみんな各自、勝手に動く。
多分、本来団体行動って日本人にはあまり向いていなかったんじゃないでしょうか。江戸時代に団体の参詣が流行るまでは。
これは会議でもそうですね。私は「和の会議」が大切だと思っています。「和の会議」のゴールは「三人寄れば文殊の智慧」の発現です。誰の意見が一番いいかなんてのはダメで、会議に集まるまでは誰も考えていなかった、まったく新しい知見が出現する、それが「和の会議」です。そのために最初にすべきことは、自分の意見をまず捨てること。あの人はああ言う意見を言ったけど、それを取り入れたら面白いかもしれない、この人のこれも面白いとか、尊重し合う。そのうちに「おお、そんな手があったのか」というまったく新しい知見が出現する。それを待つのが「和の会議」です。
西洋的“Individual”との違い――「あわい」で結ばれる日本的な自己
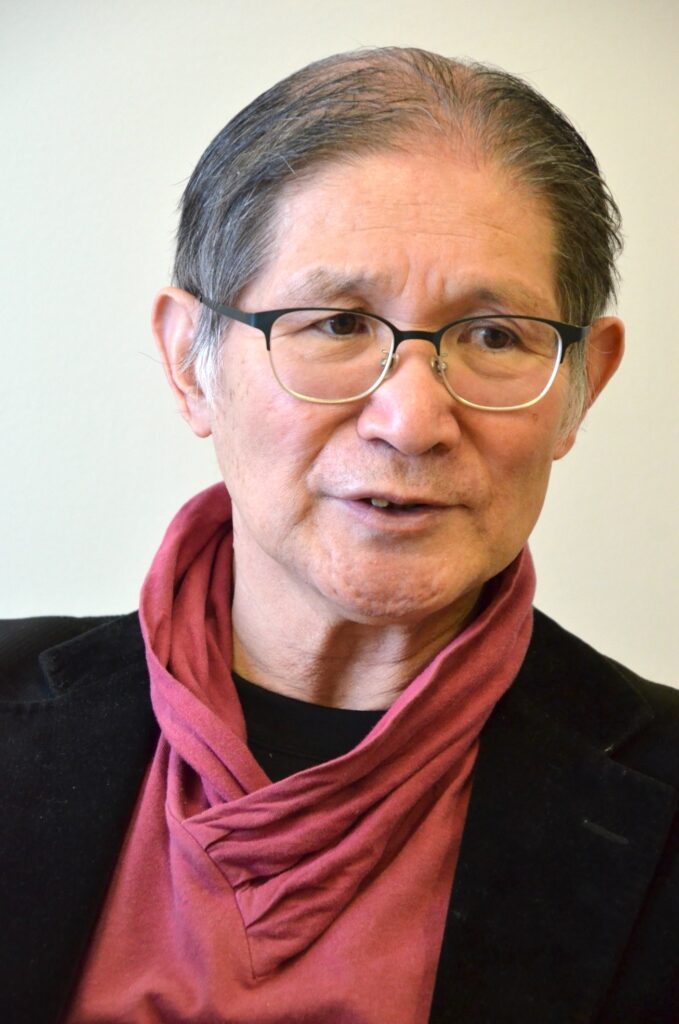
安田 西洋の“Individual”という概念は、日本の「孤」の理解と根本的に異なります。西洋的な「孤」は、個人主義を基盤とし、自分自身を守るために壁を作り、他者との関係を遮断することがあります。
RES 和すことができない、もうこれ以上分解できないのが西洋式の「孤」ってことですね。
安田 一方で、日本的な「孤」は、他者や自然との間に“あわい”(*1)を作り、つながりを維持しながら自己を深めるものです。
RES とすると、『日本人の身体』の中で書かれた「現代は、『孤』の道を歩んでる」というのはどちらかというと、西洋式の道を歩んでるという意味で言われたのですか?
安田 西洋的な自己というのは、自分の周りに膜を作り、内と外を分けるという考え方が基盤になっています。「生命」の定義としてチリの生物学者ウンベルト・マトゥラーナとフランシスコ・ヴァレラはオートポイエーシスという概念と説きました。生命は自分の周囲に膜を作る。すなわち、自己を閉じたシステムとして自己を再生産、維持していく仕組みだと捉えます。
一方、免疫学者の多田富雄さんがスーパーシステムという概念を出していて、この考え方も重要です。スーパーシステムは、自己の枠を作るだけでなく、その枠に外部の影響を取り込む仕組みを持っています。例えば、免疫システムは外部からの異物を攻撃することで自己を守りますが、偶然入って来てしまった異物はその時点で「内部」になります。「自己」とは常に自己言及的であり、自己を変化させ続ける仕組みを持っているのです。これは面白い考え方ですよね。私は今68歳ですが、3歳のときの安田登と68歳の安田登は全く別人です。3歳の時の私は、様々なものを取り入れて、自己を拡張していって、その間に傷ついたりとかしながら、どんどん拡張する。この膜は、実は完全に閉ざされた膜ではなくて、常に「あわい」である膜です。
「あわい」というのは「あいだ(間)」に似ていますが、少し違っています。「あいだ(間)」は「空き処」からできたことばで、AとBの間隙を意味しますが、「あわい」は「逢う」からできたことばでAとBの重なる空間をいいます。別物であるAとBは「あわい」によって常に繋がっているのです。
RES そのあわいは、学習や教育と重なる部分はありますか?
安田 学習というのは、学ぼうとする対象と自己とのあわいを形づくっていく作業だと思っています。そして、たとえば外国語を習得すると、世界を見る目が変わるように、自己が変容するスーパーシステム的でもあります。
「稽古」という言葉の由来にもそれが表れています。稽古の「稽」は、頭を地につける拝礼です。そして「古」ですが、この字はヘルメット(兜)の形だと言われています。「囗」で囲むと「固」という漢字になるでしょ。そこから不変のもの、そして古いものという意味になります。つまり、稽古とは不変なもの、古代のものに対して敬意を払い、学ぶ姿勢を取る行為をいいます。稽古をすることによって、古代のもの、すなわち時間すらも超越する「あわい」を形づくることができるのです。
学びと身体知の話をする上で、私の基本スタンスは、身体で理解できないことは理解したふりをしないということです。『おくのほそ道』は実際に歩いてみなきゃわかんない。論語だって書かれたことを実行してみないとわかんない。そういう考えに至ったのは、アルバート・ノーランという人の影響が大きい。アルバート・ノーランは南アフリカの神学者で、アパルトヘイトの時代に「もしここにイエスがいなければ、イエスは存在しないのではないか」と考え、そこでの人々の生活や痛みの中にイエスを探し始めた。彼の著書『南アフリカにいます神(God in South Africa: The Challenge of the Gospel)』では、福音というものは、本来は人々を立ち上がらせ、歓喜させるものであったはずだと述べています。

RES 福音、つまりゴスペルの本来の意味を再考したわけですね。
安田 そうです。本来、ゴスペルは“グッドニュース”、つまり良い知らせを意味します。それを聞いたら、その瞬間に皆、立ち上がって踊り出すほど嬉しいはずだと。しかし、現代の教会で語られる福音(ゴスペル)は、人々がそのニュースに歓喜して立ち上がるどころか、もしテレビのニュース・クルーが来たら、そのつまらなさに帰ってしまうのではないかと。そこで、ノーランは本当の福音とは何かというのをアパルトヘイト下の南アフリカで探し始めるのです。それを読んで私は「論語」もまた本当に力があるならば、人々に変化をもたらすはずだと考えました。そこから「論語」を使った実践を始めました。
そのひとつが、毎週1回、引きこもりの若者たちと集まり、「論語」が役に立つかを一節をテーマにして実践するということでした。例えば「論語」の一節“学而時習之”。まずは、この文の意味を説明し、その中から特に「学」の漢字を成り立ちや意味など詳しく話します。
「学」は、学舎に入れた子弟を、両手を使って身体的に教えるという文字です。日本語の「まなぶ」も「まねぶ」ですから、身体的には何かの真似をします。つまり、何かを学ぶには身体で教わり、身体で学ぶこと。そして模倣することが大事だということです。
それを一週間意識してみる。そのために「学(學)」という文字を書いた紙片をポケットに入れておく。忘れそうになったときに、取り出して思い出す。そんなふうに、1週間「学」を意識しながら生活してもらいます。毎日、夜、SNSで連絡しあって、今日どうだったかを聞く。できなかったらできなくてもかまいません。ただ、これを毎週、1枚ずつやっていきます。
RES この方法で、論語のエッセンスを身体的に体感するわけですね。
安田 「学」がピンとこない人もいます。しかし、次週の字で何かを感じるかも知れない。これを続けていく中で「論語」には力があるんだということを実感しました。
この取り組みの中で気づいたのは、「論語」で使われる漢字の多くが身体的な文字だということでした。「論語」冒頭の「学而時習之」の漢字も、すべてが身体的な文字です。
ここから生まれる「身体性」を無視して学びを進めることはできません。
ちょっと面倒なことをいいますと、「からだ」と「身体」と「身体性」というのは分けて考えた方がいいと思っています。「からだ」の語源は「殻」です。身を抜いた部分ですね。ですから、昔は「からだ」というのは死体のことをいいました。英語の「body」にも死体の意味があります。それに対して、内部は「み(身)」、これは「実」です。殻(=からだ)の内側をいいます。能のような芸能では「からだ(殻)」で激しい運動をするのではなく、「み(実)」による充実した動きを重視します。
「身体」というのは、この「からだ」と「み」を含む言葉ですが、しかしそれでも指すのは皮膚の内側です。しかし、「身体性」と言ったときには、そこに留まらない。たとえば、能楽師がサシという型をします。これは形としては、ただ腕を伸ばして、扇で空中を指すだけの形ですが、しかしその身体性は扇を握る手や扇に留まらず、そのずっと先、観客の遥か後ろまで届いています。これが「身体性」です。「身体性」は「身体」を超えて、もっと広がりを持つものなのです。かと言って、それを抽象的に考えちゃいけなくて、本当にそのときにぐっと引かれる感じがあるかどうか。
RES この身体性も、あわいの概念と繋がっているのですね?
安田 はい。能舞台の上では、実際に触れあうことはほとんどありませんが、「身体性」によって触れ合うことはよくあります。また、皮膚は世界と自分の内側を繋ぐ“あわい”そのものです。このあわいの器官をどう活用し、調和させるかはもっと考えたいところです。
*1 あわい
安田さんは、『日本人の身体』の中で「あわい」について以下のように語っている。
『東洋人にとっての「境界」とは、点や線ではなく、なんかそこら辺一帯をいうのです。点や線というものは、物理的には空間や質量を持ちません。しかし、そこら辺一帯である界隈としての境界は空間も質量も持っている、れっきとした場所なのです。
そのような曖昧な境界をいう言葉として、日本語には「会う(会ふ)」という語から派生した「あわい(あはひ)」という言葉があります。』(同書p94〜95)
安田登(やすだ・のぼる)
1956年千葉県銚子市生まれ。能楽師のワキ方として活躍するかたわら、甲骨文字、シュメール語、論語、聖書、短歌、俳句等々、古今東西の「身体知」を駆使し、さまざまな活動を行う。
【主な著書】
『あわいの力~「心の時代」の次を生きる』『すごい論語』(以上、ミシマ社)
『異界を旅する能~ワキという存在』(ちくま文庫)
『能~650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)など。