『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
勝つためだけの身体から、「感じる」身体へ──平尾剛氏が語る、スポーツと学びを結ぶ身体知の哲学@【教育サービスR&D勉強会 #005】 身体知の時代 ~身体知が学びの新たな地平をひらく vol. 3~

2025年3月30日、『【教育サービスR&D勉強会 #005】 身体知の時代 ~身体知が学びの新たな地平をひらく vol. 3~』が開催された。ここでは、平尾剛氏(神戸親和大学教授(当時)、現成城大学教授)のパネルプレゼンテーションを紹介する。 スポーツにおける「勝利」は、しばしば唯一の価値基準として立ち現れる。しかし、その過程で何が失われているのか。元ラグビー日本代表でもある平尾氏は、自らの経験と研究を通して、「身体で感じること」「言葉で掴み直すこと」の重要性を語る。
「根性でなんとかなる」からの出発
平尾氏のラグビー人生は中学1年生から始まった。当初はバスケットボール部に入るも、真面目に練習しない環境に失望し、誘われるままにラグビー部へ。そこにあったのは、水も飲ませず、「気合と根性」がすべてを支配する文化だった。平尾氏は述懐する。
「そこから高校2年生までおそらくそこら辺にいるスポーツをしている部活に励む人たちと同じで、言葉で理解するというよりも根性、精神ですよね。まだまだ水飲んだらあかん時代でしたしね」 高校に進んでもその風潮は変わらない。2時間の練習の中で水を飲めるのは一度か二度。体調不良でも「走れば治る」とされる世界で、身体は鍛えるよりも「耐える」ものだった。
だが、やがて転換を迎える。筋力トレーニング、いわゆる“ビッグスリー” (ベンチプレス・スクワット・デッドリフト)が高校3年時に導入され、身体が劇的に変わっていく。筋力の増加が視覚化され、パフォーマンスが向上する。これを機に平尾氏は「科学的な身体」への信頼を深めていった。
科学では割り切れなかった“身体の声”
大学から社会人、そして日本代表。トレーニングはより緻密に、よりデータに基づいたものとなり、試合の戦術も秒単位で設計されるようになった。ラグビーのプレー継続時間は平均40秒とされ、その40秒にすべてをかけるようなトレーニングに没頭した。
しかし、30歳を迎えたころ、突如として「原因不明のめまい」に襲われる。病院をいくつも回っても、視神経や身体には異常がないと診断され、「気のせいでは?」とさえ言われた。
「頭では理解していましたが、医学できちっと原因がわかるというか、診断がきちんと下される病とか怪我だけじゃないじゃないですか、世の中っていうのは。でも、根性から科学への傾倒があって、科学を信じてきた身としてはなぜ分からへんねんと。科学ってもっと進歩してたんちゃうの?と自分の症状が医学では解明できないことに怒りと焦りが湧きました。原因が明確にならない病って、わりとあるんですけどね。周りからは「気持ちの問題ちゃうか」って言われたりもしました。気のせいやと。つまり神経質すぎるんやと。気のせいなんかじゃないんですよ、右側にいる人が二重に見えてるんです、現実に。当時が30歳だから、ラグビー選手としてはピークを過ぎかけてる年齢で、あと何年選手でいられるかというところだったから、ケツに火がついてたんですよね」と平尾氏は述懐する。その経験が、平尾氏を“感じる身体”へと向かわせた。
「科学で解明できるはずだ」と信じていたはずの自分が、科学の網からこぼれ落ちていく。その経験が、平尾氏を“感じる身体”へと向かわせた。「見える異常」ではなく、「語れない違和感」こそが、身体知の入り口だった。
武術の身体──「予備動作を消す」ことで浮かび上がる知
転機となったのが、武術研究者・甲野善紀氏の研修会だった。そこで平尾氏は、自分より30キロ以上軽い甲野氏に、まったく手も足も出なかった。
「目で追えない」「触れようとしてもかわされる」「懐に入ったと思ったらすでに遅い」。それは筋力やスピードといった従来の“身体パラメータ”では説明できない現象だった。
武術の身体は、いかなる予備動作もなく、動作を発動する。視覚に映らない“感覚の差”が、空間を支配する。「予備動作を消す」というこの考え方は、平尾氏の身体観を根底から覆した。 このとき初めて、「身体の質」という言葉が意味を持った。質量や筋力ではなく、「動きの質」「反応の質」「感覚の質」が、真の“強さ”を規定する。
習得は一直線ではない──「戻りながら進む」身体の学び
講演では、運動習得のプロセスについても紹介された。平尾氏は発生論的運動学をもとに、次のように説明する。
- 原志向位相──やってみたいという動機
- 探索位相──どうやればできるのかを探る
- 偶発位相──たまたまできる
- 形態化位相──再現できるようになる
- 自在位相──どんな場面でも使いこなせる
これらは階段のように一方向に登っていく「段階」ではなく「位相」であって、状況によって何度も行き来する「往還的なプロセス」だという。
「例えば、一度“偶発的にできた”技が1ヶ月後にはまたできなくなっていることもある。そうなったときに『自分にはセンスがない』『ダメなんだ』と思う必要はない。単に“プロセスが戻った”だけなんです」と平尾氏は語る。
この考え方は、アスリートに限らず、あらゆる学びの場において示唆的だ。新しいスキルを身につけるとき、つい“できる・できない”の二元論で自分を評価してしまいがちだが、平尾氏は「そのどこに自分がいるのかを把握すること」の方が大切だと言う。
さらに、こうしたプロセスの違いは個人差にも表れる。いきなり偶発的にできてしまう「飲み込みの早い人」もいれば、探索位相が長い「言葉を必要とする人」もいる。前者は運動神経が良いと見なされがちだが、後者は指導者になったときに強みを発揮することが多い。自分で悩み、工夫して乗り越えた経験があるからだ。
このような視点を持てば、スポーツ指導のあり方も変わる。平尾氏は、「トップアスリート出身の人ほど、“俺はすぐできたから”という前提で指導してしまいがち。でも、それが全員に当てはまるわけではない」と指摘する。
「学びは戻りながら進むもの」。この循環的な身体の習得観こそが、平尾氏の語る“身体知”の核心のひとつだ。
言葉による身体知の探究──“わざ言語”という思想
現役を引退した平尾氏は、その「質」の正体を探るため、言葉での再構築を試みた。身体で経験した“しっくりくる感覚”を、言葉に置き換えてみる。そこから彼は、“わざ言語”という概念にたどり着く。
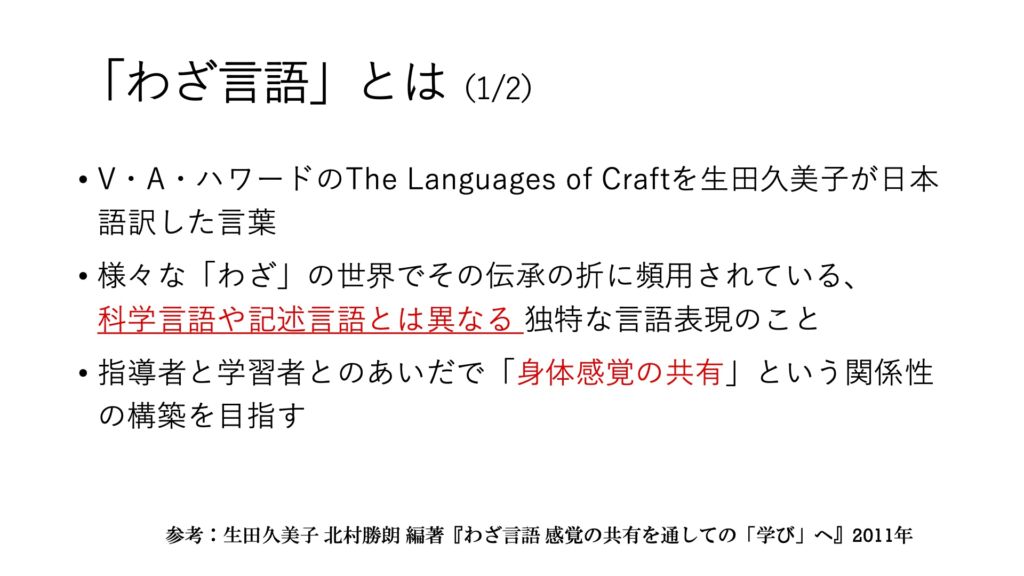
作成:平尾剛氏
「スーっと走る」「ドンと構える」「ドタドタ走る」など。これは論理的な説明ではない。しかし、身体感覚を共有するには、こうした“感じの言葉”が不可欠なのだという。科学的な記述言語では掬いきれない身体のニュアンスが、わざ言語には宿る。
わざ言語とは、身体の内部にある「気配」や「違和感」「しっくりくる感触」を他者と共有可能にするためのメディアだ。これにより、「感覚の再現性」が高まり、学びが深まっていく。
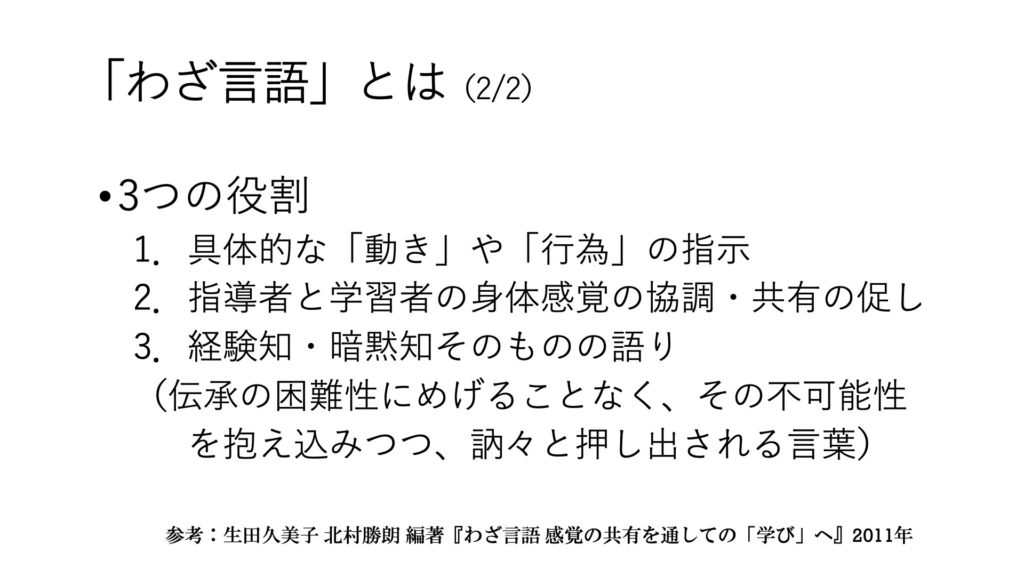
作成:平尾剛氏
競争主義と勝利至上主義──“暴走する目標”のリスク
スポーツの本質には競争がある。平尾氏も、「競争自体は悪ではない」と認める。むしろ、競争によって互いを高め合うのがスポーツの魅力だ。
「競争主義ってちょっと負けず嫌いの子どもたちをお互いに競わせるとやる気になるからで、結果的に両方いいライバルになって、全体の質を高めるというのが目的で使われているんですけど、これが行き過ぎると勝利至上主義になるんですよね」
だが、それが“勝利至上主義”に転化することで、学びのプロセスが圧殺されてしまう。平尾氏は「競争主義が暴走して勝利主義主義になる」と明言する。これはスポーツだけではなく、教育現場でも同様だ。プロセスを重視せず、「できた人」だけを選抜する構造は、学びの本質を歪めてしまう。重要なのは、「勝つこと」ではなく、「学んでいくことができる環境」をいかに保障するかだと平尾氏は問う。
「結果を出した者だけが選ばれ、途中の努力は評価されない。勝つことがすべてになったとき、身体知を探る時間はなくなる」
教育現場でもこの構造は再現されがちだ。「できる子」が選抜され、「まだできない子」が見過ごされる。そうではなく、「できるようになるまでのプロセス」にこそ、教育の本質があるのではないか。平尾氏は最後にこう語った。
「競争主義が暴走して勝利主義主義になる。こういうことをきちんとスポーツに関わる、自分でプレーする、あるいは指導することにおいて理解しておくことが、結果的に自分の感覚を探ったり、自分でしっくりくるような言葉をあてがったり、そういう身体知というものを豊かにする上で、非常に大切なことだと思っています」。
身体は問いを持ち、感覚を発し、言葉を欲する存在だ。筋肉でも理論でもない、「感じ取る力」こそが、学びの出発点である。自分の感覚を言葉で掴み、それを他者と分かち合う──その営みが、知の共有であり、教育の核なのである。

平尾 剛(ひらお・つよし)
1975年大阪府出身。神戸親和大学教育学部スポーツ教育学科教授。同志社大学、三菱自動車工業京都、神戸製鋼コベルコスティーラーズに所属し、1999年第4回ラグビーW杯日本代表に選出。2007年に現役を引退。度重なる怪我がきっかけとなって研究を始める。専門はスポーツ教育学、身体論。
【主な著書】
『スポーツ3.0』『近くて遠いこの身体』『脱・筋トレ思考』(以上、ミシマ社)
『合気道とラグビーを貫くもの――次世代の身体論』(共著 内田樹、朝日新書)
『ぼくらの身体修行論』(共著 内田樹、朝日文庫)など
