『RESmedia』は、「すべての教育の知見と情報をRESmediaに」を目指し、カテゴリーの壁を超えた新しい教育の形を探究するポータルサイトです。
2030–40への見取り図
A やっぱりこの本のいいポイントは短期的にはもう過ぎちゃいましたが、2020年ごろまでの学びの個別化、協同化の充実、対応した教員養成教育行政の支援の充実で、ここから30年から40年頃までの中長期でいうと、学びのプロジェクト化の充実、カリキュラムの市民が、一般福祉のための学びのネットワーク化みたいな話があって、RESとして苫野さんに、このあたりをちゃんと、どれぐらいの時間軸でやれてると思いますか?という話をして、この30年から40年あたりに向けた動きを、どういうふうに作っていくかっていうのは、結構必要なんじゃないかなと思うんですよね。
で、まあ親の世代も変わるでしょうし、少子化の動きとかも、想像以上に、ここ3年ぐらいでもう70万60万になっていて。
どういうふうにやっていくかって、こういう話じゃないかと思いますけどね。だから問題意識としては、時間の流れの中でできることっていうのは、せいぜいが加速するっていうことなんだけど、着実に適切な方向と我々が考える方向に加速させられるかどうかっていうことじゃないですかね。どうですか? もっと悲観的?
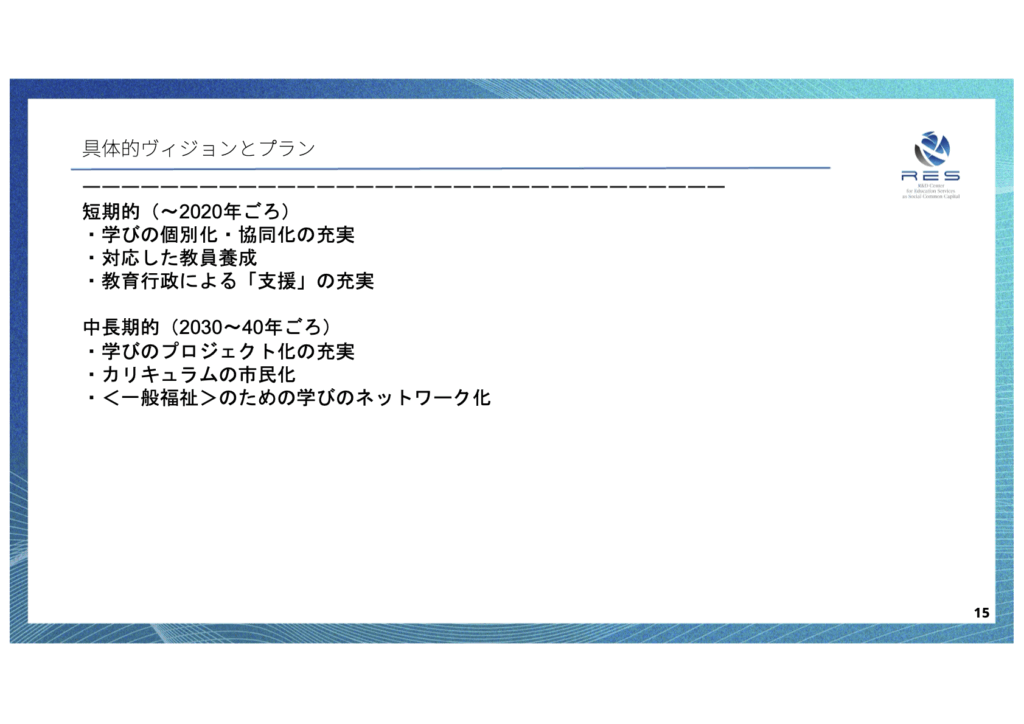
作成:RES
D 私は全然悲観的じゃないです。むしろ楽観的で。でも、今申し上げたように、団塊の世代が一掃されて、自分らの新人類と言われた60代前後の人らが一掃されると、結構、教育の現場ってまた新しい動きが見えてくるだろうなと思うんです。文科省っていうのはその辺の時間軸というのはやっぱりお持ちで、今の教科書なんか見てると、今回マニアックな話ですけど、指導要領って10年に一回大きく改訂されるんですけど、教科書検定は4年に一回で、(これまでは)大したことないんですよ。ほとんど教材会社もちょろっといじるぐらいになりがちだったのが、今回、4年に一回の教科書改訂にもかかわらず、結構意欲的な会社がまあまああるんですね。その辺を見ていると、教科書会社も危機感を非常に持ってるし。まして、紙媒体がもう終わりかもしれないと言われてるから余計かもしれないんですが、4年に一回の改定でここまで力を入れるんだなぁっていうのは、今までになかった変化だと肌感覚であるんですよ。
A なるほどね。
C 私もすごい楽観的な立場でして、本当少子化の影響を受けながら、大学入試も今変わってきているなっていうのは、ここ10年ぐらいで感じています。子どもが減るので、大学も早めに学生を取らないといけないっていう思惑とかもあるとは思うんですけれども、それこそ総合型入試に変わってきていることであったり、いわゆる知識偏重型のものだけではなくて、もっと総合的に評価をするような形が進んでいるのかなとは思います。
ただ総合型といっても、単に志望理由書を出させて、合格させてしまうみたいなところもあったりするので、はたして本当に基礎学力とかを担保できてるのかっていう別問題はあったりはするんですけれども。なので、そういった個別化であったり、協同化であったり、生徒の個性をより伸ばしていくみたいなところが受け入れられていく。教育っていうのは、徐々に徐々に進んでいるのかなとは認識はしています。
A そういう意味では、この苫野さんの話について何か違和感とかはないですか?
C 苫野さんの話には違和感はないんですけど、その先ほどあったきのくにの話であったり、風越学園であったり、こういう教育の形が分断されつつあるなっていうのは、すごい思ってまして。
A 分断?
C はい。風越学園に通ってる生徒と話す機会があったんですけど、風越学園は中学生までなので、高校はどこに行くかっていうと、それこそ神山高専であったり、FC今治の岡田監督の作った高校(FC今治高等学校)であったりで。大学はSFCに進学しますだったり、起業しますだったり、結構、進路が、なんなんでしょう、そっちよりの進路というか、もう固定化されてしまうっていうのは課題としてあります。
D きのくにが抱えておられる問題と全く同じですね。
B 逆に進路が狭まるって話ですね。
D そうなんですよね。高専系に行くか、大阪芸大に行くかみたいなね。
B 逆に言うと、だからその上の高校なのか、あるいは大学なのか。要は多様性をもっと広げていかなきゃいけないっていう話ではありますよね。そこは、高校、大学がまだ旧来型であるからゆえに、選択肢が少ないということになっていると思うんですよね。
A いや、ここは僕の問題意識を言うと、最大の課題はやっぱり協同的な学びのベースになる〈教養=力能〉みたいなものを、社会全体がちゃんと共通基盤に持ち得るかっていうところ。これを促すような形にやっぱりなってないんだと思うんですよ。で、そこを文科省はわかってますかっていう話なんですよね。
で、多分、教科書会社は、その教科書に書くべきことはすごく共通の基盤になるものにして、副教材でそこを補うっていう方向でやろうとしている。この考え方はいいと思ってね。ただ、やっぱり毎日みんなグーグルに接して、フィルターバブルの中でエコチェンバーやっててね。それで、風越だけでプロジェクトやったり、きのくにだけでプロジェクトやったりしてたって、じゃあ、他の学校の子たちとどれぐらい、まさにその共通了解に至るようなディベートができますか?とか、そういう機会がありますかとかっという話だと思うから、やっぱり社会的な学びのネットワークをもっともっとつなげていくっていうことが重要で。それは国にはできないわけよ。で、それをRESはやる。私はそれがRESの意義だと思ってるんですね。
やっぱりね、「教養」ってことをわざわざ書いてるっていうのは、結局お互いにレファレンスポイントっていうものが入って、共通のものがないと、やっぱり議論になりようがないんですよね。
多分ね、そこまで苫野さん考えていると思うんですけど、そういったところまでちゃんとみんな分かってるかっていう私は疑問なので、ちょっと苫野さんと話して、「そうですよね」っていうところで共感を得るとですね、RESがまたやる領域も広がってくるかなっていう気がしますけど、どうですか? まあ一応、うなずいていただいて(笑)。
私は、一番は個別化、協同化というのは、大人でまずやるべきだと思うんですよ。
大人が今、多分、この相互依存関係の強い世界の中において、自分がどこにどういるのかすら分かっていない。これをちゃんと押さえる教育をやって、初めて学ぶ力というものを、大人が実践しているのを見て、子どもが面白いなって思う。やっぱり面白い大人がいれば、子どもは学ぶんだっていう話。だから子どものことを言う前に、まず隗より始めよっていうことじゃないの?ってならないと。
多分、内田樹さん――次回以降取り上げる予定の越境、複雑化する教育のあたりの話にも絡むんですけど――「越境」ですよね。で、こういうものをやっぱり本質的にソルブしないと、ベースとしての個別化と協同化の話は、立ち行かんのだっていうことが、みんなわかってますか? エコーチェンバーの話が1つも出てない個別化、協同化の話なんてありえないんですよね?と、ちょっとつい主張しちゃうんですけど、Cさんどうですか?
C おっしゃる通りですね。個別化、協同化なしに、先ほどの自由みたいなところは出てこないと思いますので。100%同意してます。
自治体スケールで学びをつなぐ
A じゃあ、そこから先どうするっていう話なんだけど、私は1つあると思うのは、その学びのネットワークとか協同化、個別化がやっぱり一番最小単位で実現し得る世界っていうの、やっぱり自治体ぐらいの感じかなと。
学校はあくまでもシステムの一部にしか過ぎないし、教育自体もシステムの一部にしか過ぎないはず。やっぱり自治体クラスなんだよね。それが5%でもいいからちゃんとしたモデルを作る。これをどういうふうにやれるかなっていうのは1つあるし。
あと今度、ここは実は資本主義は外せないので、国家産業的な観点で行くと、やっぱり、そろそろ道州制みたいなのは考えてもいい時期で、自治体ごとの経済というものと合わせた教育システムっていうのがあるし、社会システムっていうのがある。そこの構想まで行くかどうかですかね。あと10年、20年の話を考えたときに。
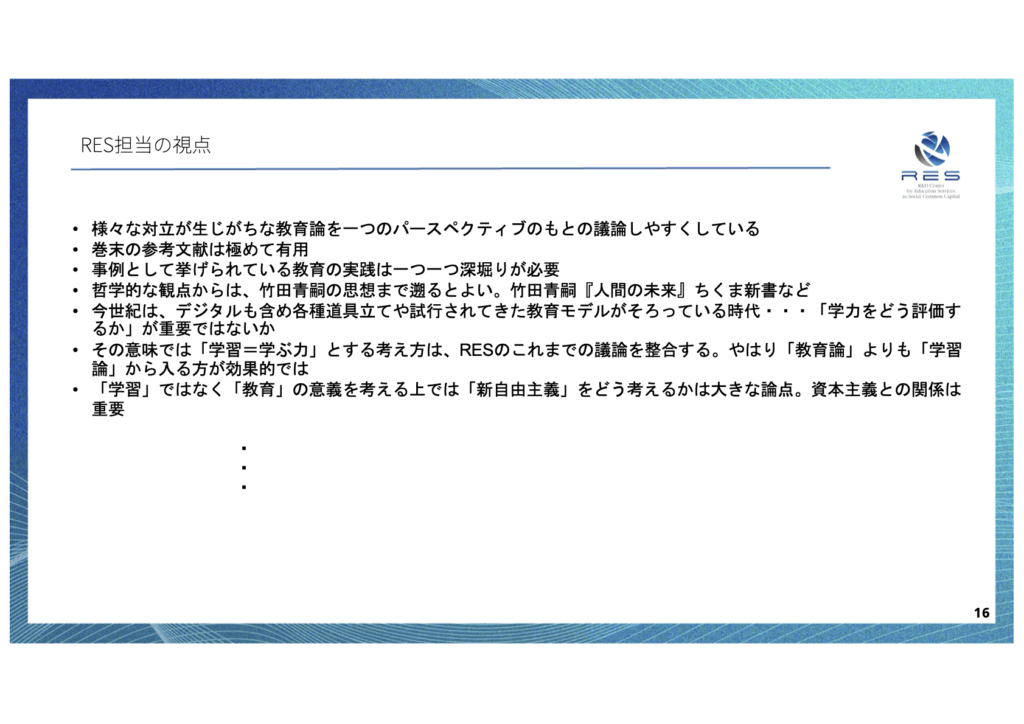
作成:RES
ちょっと私の問題意識はそんなところにあるっていうのをつい喋っちゃいました。もう時間が過ぎているので、最後まとめに入るとですね、RES担当の視点としては、さまざまな対立が生じがちな教育論を、1つのパースペクティブを元に議論しやすくしてますよねと。で、我々としては巻末の参考文献は極めて有用なので、これはもっと深掘っていくためのベースができるっていうこと。
それと、学力をどう評価するかっていうところで、学び方、学ぶ方に軸足を送っているRESのスタンスは悪くない。アプローチとしてやっぱり悪くないけれど、学力っていうのをどう評価するか、本当にこれは難しいです。で、どう難しいかと言ったら、やっぱり何のための学ぶ力だっていうことなんですよね。これも人類史的な話になっちゃうわけですよ。別に学ばなくたっていいじゃんかっていう発想だってあり得るわけですよね。自分の生活の中で、心地よいものがぐるぐる回ってれば、それを深掘りするだけでもいいよねっていう発想だってあるわけで。それがダメなのかって言われたら、必ずしもダメじゃないわけじゃないですか。でも先生は学ぶ力に常に関与してないとダメだとは思いますけど。
それから、学習論から入る方が効果的という話と、やっぱり学習ではなく、逆に教育の意義を考える上では、新自由主義というのをどう捉えるかという話が整理されてないと、教育論そのものの方ができない。文科省はどうしても、教育論の方をしなきゃいけないんで、ここがかわいそうなところというか、難しいところなんだよね。だって、新自由主義に代わる答えはないんだもん、文科省は。それを民主主義的に決めなきゃいけない話なんだけど、石破さんにそんなことリードできるわけないし。それこそ、新自由主義に代わる発想なんて、日本人の誰も持ってないですよね。たぶん、そういうところに、教育論をしたいんだったら戻るという難しさが本質的にあるんじゃないかっていうことを、投げかけて終わりとしたいです。
RES編集部
